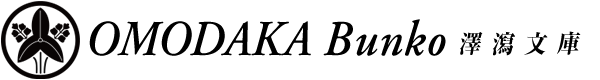いつものようにブラインド・タッチの練習用にと、適当に選んで初めたんだけど、この作品は時間がかかりました。
少し辛い作業でした。
しんどくて、なかなか先に進むことができずに停滞を繰り返してしまいました。
ときどきこういう作品に出会うことがあります。
ミステリーなどは文字通り、寝る間を惜しんで一気に読み進んでしまうことが、良いミステリーの証だけど、文学作品の中には稀に良品故に先に進むことができなくなってしまう作品があります。
良い作品に間違いはないんだけど、読み進むのが辛く、琴線に触れすぎちゃって心拍数が上がって先へ進めない作品。
ウォン カーウァイの映画『花様年華』なんかも、すごくいい映画なんだけど、切なすぎて、かえって先が見られない…
もうドキドキしちゃって、続きを見るのが怖くなってきちゃう…
この『足もとに流れる深い川』もそんな作品です。
秘められた狂気と、危うさゆえに、先へと読み進むのが辛くなるような短編でした。

+++++++++++++++++++++
足もとに流れる深い川
Raymond Carver
食欲こそ旺盛だったが、夫は疲れて苛々しているように見えた。彼は両腕をテーブルの上に置き、ゆっくりと口を動かしながら部屋の向こう側をじっとにらんでいる。彼は私をちらっと見て、それからまた向こうに目をやる。そしてナプキンで口を拭う。肩をすくめ、食事をつづける。彼はそう認めたがらないかもしれないけど、私たち二人のあいだを何かが隔たてている。
「なんだってそんなに俺をじろじろと見るんだ?」と彼は言う。「なんだっていうんだよ?」そしてフォークを置く。
「そんなにじろじろ見てたかしら?」と私は言って頭を振る。すごく不自然な感じだ。
電話のベルが鳴る。「でるなよ」と彼は言う。
「あなたのお母さんからかもしれないわ」と私は言う。「ディーン――ディーンのことじゃないかしら」
「じゃ、まあどうぞ」と彼は言う。
私は受話器をとり、しばらく相手の話を聞く。夫は食事の手を止める。私は唇を噛み、電話を切る。
「言っただろう」と彼は言う。そして食べ始めるが、やがて皿の上にナプキンを放り出す。「畜生め、なんだってみんなお節介ばかり焼くんだ。俺が何か間違ってたことをやったっていうのなら、ちゃんとそう言えばいいじゃないか。こんなのってないぜ。女は死んでたんだ。そうだろ? そこにいたのは俺だけじゃない。みんなで相談して、それで決めたんだ。俺たちはそこに着いたばかりで、そこに来るまで何時間も歩きっぱなしだったんだ。回れ右して車までまた五マイルも歩けっていうのか。初日なんだぜ。冗談じゃない、何がいけないんだ。いったいどこが間違ってるっていうんだ。だからそんな目で俺を見るなよ。非難がましい真似はやめてくれ。君までさ」
「でも、わかるでしょう」と私は言って頭を振る。
「おいクレア、俺にいったい何がわかるって言うんだ? え、言ってみろよ。俺にわかっていることは一つしかない。このことについて君があれこれ悩んだってしょうがないことさ」彼はこういうのが思慮深げな顔だという顔をした。「彼女は死んでたんだ。しんでた。わかるか?」ちょっと間をおいてつづける。「ひどいことだよ、本当にさ。あんな若い娘がさ、ひどいことさ。俺だって気の毒だと思う気持ちにかけちゃひけをとらない。でもな、彼女は死んでたんだよ、クレア、死んでたんだ。だからもうそのことは忘れようよ。お願いだよ、クレア。忘れよう」
「そこなのよ」と私は言う。「彼女はたしかに死んでたわ――でもあなたにはわからないの? それでもやはり彼女は助けを求めていたのよ」
「負けたよ」と彼は言って両手をあげる。彼は椅子を引いて立ち上がり、煙草をとり缶ビールを手に中庭に行く。そしてあちこち歩き回ってから庭椅子に腰を下ろし、新聞をもう一度手に取る。その第一面には彼と彼の友人たちの名前が載っている。「惨事の発見者たち」の名前だ。
私は目を閉じて水切り台にじっとしがみつく。こんな風にいつまでもくどくどと思いわずらっていてはいけないのだ。そんなことは忘れ、頭から追い払い、何でもいいとにかく「先に進む」のだ。私は目をあける。でも結局(そんなことをしたらどうなるかよくわかっていたのだけど)水切り台の上で手を払って、皿やグラスを床に落として割ってしまう。かけらが床じゅうに飛び散る。
夫は動かない。彼がその音を聞いたことは明らかだ。彼は聞き耳を立てるように頭を上げる。しかしそれだけだ。振り返りもしない。私は彼を憎む。振り返りもしないなんて。彼はちょっと間をおいてから椅子にゆっくりともたれかかり、煙草を吹かす。哀れな人だと私は思う。耳だけをそばだてて、平気な顔で、そのまま椅子にふんぞり返って煙草を吹かしているなんてね。煙草の煙が風に吹かれて細くたなびいている。どうして私はそんなことに気が行くんだろう? 私が哀れんでいるなんて、あの人にはわかるまい。じっと座って耳を澄ませ、煙草の煙を風にたなびかせていることに対して私が可哀そうだと思っているなんて……。
夫が釣り旅行に行くことに決めたのは先週の日曜日、戦没将兵記念日のある週末の一週前だ。彼とゴードン・ジョンソンとメル・ドーンとヴァーン・ウィリアムズ。彼ら四人は一緒にポーカをやったり、ボウリングをしたり、釣りをしたりする仲だ。彼らは毎年春と夏の始めにみんな揃って釣りに行く。シーズン初めの二ヶ月か三ヶ月、家族旅行やリトル・リーグ野球や親戚の家を訪問したりで忙しくなる前だ。みんなきちんとした人たちだ。家庭を大事にして、責任ある地位についている。みんな子供がいて、うちの息子のディーンと同じ学校に入れている。金曜の午後、彼らはナッチーズ川に三日間の釣り旅行に出かけた。山の中に車を停めて目的の釣場まで何マイルか歩いた。みんな寝袋と食料と調理用具とトランプとウィスキーを用意していた。川についた最初の夜、まだキャンプを設営していないうちに、メル・ドーンがうつ伏せになって川に浮かんでいる娘を発見した。彼女は裸で、川岸から突き出た枝にひっかかっていた。彼はみんなを呼び、みんなはやってきて彼女を眺めた。彼らはどうすればいいかを話し合った。一人が――スチュアートはそれが誰だかは言わなかったけれど、たぶんヴァーン・ウィリアムズだろう。体格の良い気楽な男で、よく大声で笑う――すぐに車のあるところまで引き返そうぜ、と言った。他の三人は靴で砂地をかきまわしながら、そこまですることはないんじゃないかな、と言った。とても疲れていたし、時間も遅いし、それに娘が「どこかに行ってしまう」わけでもないのだ。結局戻らないことになった。彼らは作業をつづけ、テントを設営し、火を焚いて、ウィスキーを飲んだ。ウィスキーを一杯飲み、月あかりの下でその娘の話をした。死体が流れちまわないように何かしといた方がいいんじゃないかな、と誰かが言った。死体が夜のあいだにどこかに行ってしまったら自分たちの立場が悪くなるかもしれない、と一応彼らは考えた。彼らは懐中電灯を手に、よろよろと川まで下りていった。風が吹きはじめていた。ひんやりとした風だ。波が川の砂地に打ち寄せていた。一人が(誰だかわからない。スチュアートかもしれない、彼ならそれくらいのことはできる)、俺がやろうと言って川に入り、娘の指をつかんでうつ伏せにしたまま川岸近くの浅瀬まで引っ張ってきて、ナイロンひもで娘の手首を縛り、もう一方を木の根に縛り付けた。そのあいだずっと他の三人の懐中電灯の光は娘の死体を照らしつづけていた。それが終わると四人はキャンプに戻り、またウィスキーを飲んだ。そして眠った。翌朝、土曜日の朝、彼らは朝食を作り、コーヒーを一杯飲み、またウィスキーを飲み、それぞれの釣場に散った。二人は上流に行き、二人は下流に行った。
その夜、魚とポテトの夕食を済ませ、コーヒーとウィスキーを飲んだあと、四人は川に下りて水面に浮かんだ娘の死体から数ヤードしか離れていないところで皿を洗った。そしてまた酒を飲み、トランプ遊びをし。トランプのカードが見えなくなるまで酒を飲んだ。ヴァーン・ウィリアムズだけは先に寝てしまったが、残りの三人は品の悪い小話をしたり、昔のいかがわしい自慢話をしゃべったりした。 誰も娘のことは口にしなかった。ゴードン・ジョンソンがついうっかり釣り上げた鱒の身のしまり方と川の水のおそろしいばかりの冷たさについてしゃべった。みんな黙りこんだ。しかし酒だけは飲みつづけた。誰かだランタンにつまずいて転び、悪態をついてからやっと、三人は寝袋にもぐりこんだ。
翌朝おそく彼らは目覚め、またウィスキーを飲み、ウィスキーを飲みながらちょっと釣りをした。昼の一時になって(日曜日だ)、彼らは予定を一日繰り上げてもう引きあげることにした。彼らはテントを畳み、寝袋を丸め、フライパンや鍋や魚や釣り具をまとめ、歩き出した。引きあげるとき、娘の死体には目もくれなかった。車に乗り込んでハイウェイを走り、電話のあるところで車を停めた。そのあいだ誰も口をきかなかった。スチュアートが保安官事務所に電話をかけた。暑い太陽の下で他の三人はそばに立って彼を囲み、電話のやりとりを聞いていた。彼は相手に自分たちの名前を教えた。別に隠すことはない。具合の悪いことなんて何ひとつないのだ。追って細かい指示をし、それぞれの話を聞くからサービス・ステーションで待機するようにと保安官は言った。いいですよ、と彼はいった。
夜の十一時になって彼は帰宅した。私は眠っていたが、台所の物音で目が覚めた。台所に行ってみると彼は冷蔵庫にもたれて缶ビールを飲んでいた。彼はがっしりした両腕を私の体にまわし、手のひらで私の背中を上下にさすった。二日前に出ていったときと同じ腕の感触だわ、と私は思った。
ベッドの中でも彼は手を私の体に置き、それからふと何かを考え込むようにちょっと間を置いた。私は少し体の向きを変え、それから足を動かした。考えてみれば、そのあとずっと彼は起きていたのだ。というのは、私が寝入ったときも彼は起きていたし、そのあとちょっとした物音――シーツのすれる音――で私がぼんやり目覚めたとき、外はもうほとんど明るくなって鳥が鳴いていたのだが、彼はあお向けに横になって、煙草を吸いながらカーテンのかかった窓をじっと見ていた。私はうとうとしながら彼の名を呼んだ。しかし答えはなかった。私はまた眠り込んでしまった。
私が今朝やっとベッドを出たときには、彼はもうきちんと起きていた。たぶん新聞に何か記事が出ていないか見るためだったのだろう。八時ちょっと過ぎに電話のベルが鳴った。
「うるせえ、畜生」と彼が受話器に向かって怒鳴るのが聞こえた。すぐにまた電話が鳴った。私は台所にとんでいった。「何もかにも保安官に話したとおりさ。そうなんだよ!」彼はがしゃんと受話器を置いた。
「いったいどうしたの?」と私はびっくりして訊ねた。
「座れよ」と彼はゆっくり言った。そして伸びたままのもみあげを何度も指でこすった。「君に言っとかなくちゃいけないことがある。実は釣りに行っているあいだにちょっとしたことがあったんだ」我々はテーブルごしに向かい合って腰を下ろした。そして彼は話した。
私はコーヒーを飲みながら、話しつづける夫をじっと見ていた。それから彼が私の方に押しやった新聞の記事を読んだ。……身元不明の若い女、十八から二十四歳……三日から五日間水中に放置……動機はおそらく強姦……予審は絞殺の結論……乳房と骨盤部に切り傷及び打撲傷……解剖……強姦については目下詳細を調査中。
「わかってくれよ?」と彼は言った。「そんな目で俺を見るな。いいか、つまらん真似はやめてくれ。心配することなんて何もないんだよ、クレア」
「どうして昨日の夜のうちに話してくれなかったの?」と私は訊ねた。
「べつに……なんとなくさ。それがどうかしたのか?」と彼は言った。
「私の言いたいこと、わかるでしょう?」と私は言った。私は彼の手を見ていた。がっしりとした指、毛に覆われた甲、そんな手がもぞもぞと動き、煙草に火をつけている。昨夜私をなでまわし、私の中に入ってきた指だ。
彼は肩をすくめた。「ゆうべだろうが今朝だろうがべつに変わりないじゃないか。時間も遅かったし。君は眠そうだったし、話すのは朝まで待った方が良いと思ったんだ」彼は中庭に目をやる。駒鳥が芝生からピクニック・テーブルに飛び移り、羽を整えている。
「嘘よね?」と私は言った。「その娘をそんな風に放りだしておいたわけじゃないんでしょ?」
彼はさっと向きなおって言った。「じゃ、どうすりゃよかったんだ? いいか、一回しか言わないからよく聞いてくれよ。べつに何が起こったってわけじゃないんだ。後悔するようなやましいことも何ひとつない。わかったか?」
私はテーブルを立ってディーンの部屋に行った。ディーンはもう目を覚ましていて、パジャマのままパズルを組み立てていた。私は洋服を探してやり、それから台所に戻って彼の朝食をテーブルに並べた。電話はそれからまた二回か三回鳴った。そのたびにスチュアートはぶっきらぼうに受けこたえし、腹を立てて電話を切った。彼はメル・ドーンとゴードン・ジョンソンに電話をかけ、話しをした。ゆっくりとした深刻げな話し方だった。それからディーンが食事をしているあいだ缶ビールを飲み、煙草を吸った。そして彼に学校のこととか友達のことを訊ねた。まるで何事もなかったみたいに。
ディーンは父親がどこに行って何をしていたのか知りたがった。スチュアートは冷凍庫から冷凍した魚をだしてきて彼に見せた。
「今日はあなたのお母さんのところにこの子を預けてくるわ」と私は言った。
「そうだな」とスチュアートは言って冷凍鱒を抱えているディーンを見た。「君がそうしたくて、ディーンもそうしたいんなら、それでいいさ。でも、べつに無理にそうすることはないんだぜ。とくにどうってわけでもないんだから」
「私がそうしたいのよ」と私は言った。
「あっちに行ったら泳げるかな?」とディーンはズボンで指を拭きながら訊ねた。
「たぶんね」と私は言った。「今日は暖かいから水着を持っていきなさい。おばあちゃまもたぶん泳いでいいっておっしゃるはずよ」
スチュアートは煙草に火をつけ、私たちの方を見た。
ディーンと私は車で町を抜け、スチュアートの母親の家に行った。彼女はプールとサウナのついた高層アパートに住んでいる。彼女の名前はキャサリーン・ケーン。ケーンという名前は私と同じ名前だ。それはなんだか信じがたいことのように思える。昔は友達からキャンディーって呼ばれてたんだぜ、とスチュアートがいつか教えてくれた。白っぽい金髪の、背の高い冷ややかな女性だ。彼女はいつもいつも何かを裁いているような印象を私に与える。私は事件のことを手短にぼそぼそと説明し、(彼女はまだ新聞を読んでいなかった)夕方にディーンを迎えにきますから、と言う。「水着を持たせてきました」と私は言う。「スチュアートと二人で話さなきゃいけないことがあるんです」と私は曖昧に付け加える。彼女は眼鏡ごしにじっと私を見る。それから肯いてディーンの方を向く。「元気かい、坊や?」彼女は身をかがめて、子供の体に手をまわす。私が立ち去るとき、彼女ははまた私を見る。彼女は何も言わず意味ありげに私を見る。いつものように。
家に帰るとスチュアートはテーブルに向かって何かを食べていた。そしてまたビールを飲んでいる。
少しあとで私は割れた皿とガラス食器を掃き集め、外に出る。スチュアートは芝生に仰向けに寝転んで空を見上げている。手元にはビール缶と新聞が置いてある。風が吹いていたが外は暖かく、鳥が鳴いていた。
「スチュアート、ドライブに行かない?」と私は言う。「どこでもいいわ」
彼はごろんと転がって私の方を向き、肯く。「ビールでも買いに行こう」と彼は言う。「もうそろそろ機嫌をなおしてくれよ。俺の身にもなってくれよ、な」彼は立ち上がり、通りすぎるときに私のお尻を触る。「すぐに用意するよ」
私たちは黙りこくったまま車で町を抜ける。彼は郊外に出る前に道路沿いのマーケットに車を停めてビールを買う。ドアを開けたすぐのところに新聞がどっさり積んであるのが目につく。入口階段の上でプリント・ドレスを着た女が小さな女の子に天草キャンディーをさしだしている。ほんの数分でエヴァーソン・クリークを越え、水際に広がるピクニック場に入る。クリークの流れは橋をくぐり、数百ヤード向こうの大きな池に流れ込んでいる。十人あまりの大人や子供が池の岸辺にぽつぽつと散らばり、柳の下で釣り糸を垂れている。
こんな家の近くにこんなにちゃんとした釣り場があるのに、どうしてわざわざ遠くまで出かけなくちゃいけなかったのよ?
「どうしてよりによって、そんなところに行かなくちゃならなかったのよ?」と私は訊ねる。
「ナッチーズ川のことかい? 俺たちはいつもあそこに行くんだよ。毎年少なくとも一度はね」我々は日当たりのよいベンチに座る。彼は缶ビールを二本開け、一本を私にくれる。
「それにあんなことになるなんて前もってわかるわけもないしさ」彼は頭を振り、肩をすくめる。まるで何年も前に起こったか、他人の身に起こったかしたことを話してるみたいに。
「のんびりしろよ、クレア。いい天気じゃないか」
「奴らは無実だって言いはったのよ」
「誰が? いったい何の話しだよ?」
「マドックス兄弟よ。私の故郷の町の近くでアーリーン・ハブリィって女の子を殺したの。それから首を切り落としてクリー・エラム川に投げこんだの。私とアーリーンは同じ高校だったの。その事件はまだ子供だったころに起こったの」
「なんでそんなひどい話を思いだすんだよ」と彼は言う。「頼むからよしてくれ。俺の気分を悪くしたくて言ってるのか? え、そういうつもりなのか? クレア?」
私はクリークを眺める、私は目を見開いてうつ伏せになって水面に浮かび、池の方に流されていく。クリークの川床の岩や藻が見える。やがて私は湖へと運ばれる。そしてそこでは風が私の体を押し動かすだけだ。何も変わりはしない。私たちはこんな風にずっとずっとずっとずっとやっていくんだ。今だってそうしている。まるで何事も起こらなかったみたいに。私はピクニック・テーブル越しに相手の顔から表情というものが消えてしまうまでじっと夫を見据える。
「どうしたっていうんだよ」と彼は言う。「いったい何が……」
私はほとんど無意識に夫をぴしゃりと打つ。私は手をあげたままほんの一瞬、間を置き、相手の頬に思いきり平手をくらわせる。私はどうかしている、と彼を打ちながら思う。私たちに必要なのは手をしっかりと握り合うことなのに。二人で助け合うことなのに。こんなのっていけない。
もう一度打とうとする前に彼は私の手首をつかみ、今度は自分が手をあげて構える。私は身をすくめて一撃を待ち受ける。しかし彼の目に何かが宿り、そして消える。彼は手を下ろす。私は前よりももっと速度を増しながらぐるぐると輪を描いて池の水面を漂っている。
「さあ、車にのるんだ」と彼は言う。「家に帰る」
「いやよ、いやよ」と私は言って彼の手をふりほどこうとする。
「こいよ」と彼は言う。「いいから来るんだ」
「君は間違っている」と彼は車に乗ってしばらくしてから言う。野原や木や農家が窓の外を飛び去っていく。「君は間違ったことをしている。俺に対しても君自身に対してもだ。それからディーンに対してもだ。ディーンのことを少しは考えてみたらどうなんだ。俺のこともだ。頭を冷やしてまわりの人間のことを考えたらどうだ」
いま彼に向かって私に言えることは何ひとつない。夫は路面に神経を集中しようとしている。しかし目はバックミラーに行ってしまう。目の端っこの方で、彼は私を、隣のシートで膝に顎をつけるようにして座っている私の姿を見ている。太陽の光が私の腕と頬の片側に照りつけている。彼は運転しながらビールの缶を一本あけ、らっぱ飲みし、缶を足のあいだにはさむ。そしてふうっと息を吐く。彼にはわかっているのだ。私は彼を笑いとばすこともできるし、すすり泣くこともできるのだということを。
2
スチュアートは今朝は私を起こさないつもりでいる。しかし私は目覚まし時計のベルが鳴るずっと前から目覚めていた。そして彼の毛深い脚と意識のない太い指を避けてベッドの端により、思いを巡らしていた。彼はディーンを学校に送り出してから髭を剃り、服を着て、会社に行った。二度ばかりベッドルームをのぞいて咳払いしたが、私はじっと目を閉じていた。
台所で彼の残していったメモをみつける。「じゃあ」とサインしてあった。日当たりの良い朝食用のコーナーでコーヒーを飲む。メモにまるいコーヒーのあとがついた。もう電話のベルはならなかった。それだけでも進歩だ。昨夜以来もう電話はかかってこなくなった。テーブルの上に新聞があったのであちらに向けたりこっちに向けたりしていたが、そのうちに手にとって記事を読んだ。死体の身元は依然不明だ。捜査願いもでていない。彼女がいなくなったことにどうやら誰も気づいていないみたいだ。しかしこの二四時間、人々は死体を検査し、薬物を投入し、切り刻み、体重や身長を測り、元どおりに並べて縫いあげ、正しい死因や死亡時間を調べあげているのだ。そして強姦の痕跡を。きっとみんな強姦だといいのにと思っているはずだ。強姦というのは理解しやすいのだ。遺体はキース・アンド・キース葬儀所に送られて措置を待つことになる、と書いてある。心当たりのある方は申し出るように、云々。
二つのことが明らかだった。(1)人々はもう、他人の身に何が起ころうが自分には関係ないと思っている。(2)何が起こっても、そこにはもう真の変化というものはないのだ。事件がおこった。それでもスチュアートと私のあいだには変化なんてないだろう。私の言っているのはほんとうの変化のことだ。私たちは二人とも年を取っていく。たとえば朝一緒に洗面所を使っているときなんか、鏡で二人の顔を見ると、それはもうはっきりとわかる。そして私たちのまわりでいくつかの物事が変化していくだろう。楽になることもあれば、厳しくなることもある。それは様々だ。でも物事のありようがほんとうに変わってしまうということはまずあるまい。私はそう信じている。我々は既に決定を下し、我々の人生は既に動き出してしまったのだ。そしてそれはしかるべき時がくるまでえんえんと動きつづけるだろう。しかしもしそれが真実だとしても、それでどうなると言うのだろう? つまりあなたはそう信じてはいながら、それを包みかくして日々を送っている。そしてある日事件が起こる。それは何かを変化させてしまうはずだ。それなのに、まわりを見まわしてみれば、そこには変化の兆しはまるでない。じゃあ、どうすればいいのか? その一方で、まわりの人々はあたかもあなたが昨日の、あるいは五分前のあなたと同じ人物であるかのように話しかけたり振る舞ったるする。しかしあなたは現実に危機をくぐり抜けたのだし、心は痛手を負っているのだ……。
過去はぼんやりとしている。古い日々の上に薄い膜がかぶさっているみたいだ。私が経験したと思っていることが本当に私の身に起こったことかどうかさえよくわからない。一人の女の子がいた。彼女は両親と暮らしていた。父親は小さなカフェを経営し、母親はそこのウェイトレス兼レジ係として働いていた。娘はまるで夢でも見てるみたいに小学校からハイスクール、その一、二年あとに秘書学校へと進んだ。そのあと、それからずっとあと――そのあいだ、いったい何があったのかしら?――彼女は別の町に移って電気部品会社の受付の仕事に就き、技師の一人と知り合う。彼がデートに誘ったのだ。結局、相手の目的を察して彼女は彼に身をまかせる。彼女はそのとき、ある直感を得た。性的な誘惑についての洞察のようなものだ。でもあとになってみると、それがどのような洞察であったのかどうしても思い出せない。ほどなくして二人は結婚することになる。しかし過去――彼女の過去はそのころから既にこぼれ落ちるように薄らいでいく。未来のことなど、彼女には想像もできない。未来について考えるたびに、彼女はまるで何か秘密でも抱いているみたいに微笑む。結婚して五年ばかりたったころ、何が原因だったのか思い出せないのだが、二人はかなり激しい口論をした。夫はこのとき「この事件はいつか暴力沙汰でけりがつくぜ」(「この事件」と言う言葉を彼は使った)と言った。彼女はそのことをずっと覚えている。彼女はそれをきちんとどこかにしまいこんで、ときどき声に出して繰り返してみる。時折、ガレージの裏にある砂場に膝をついて座って、午前中ずっとディーンや彼の友達の一人か二人と遊んでいることもある。しかし午後四時になるときまって頭が痛みだす。彼女は頭を抱える。痛みでくらくらする。医者にみてもらうようにスチュアートに言われて、彼女は医者に行く。医者がいろいろと親切に関心を示してくれることが正直なところ嬉しい。彼女は家を離れ、医者に勧められた施設にしばらく入ることになる。子供の世話をするために夫の母親がオハイオから急いで出てくる。しかし彼女――クレアは何もかもを放り出してしまう。そして二、三週間で家にかえってくる。義母は家を出て、少しはなれたところにアパートを借りてそこに腰を据える。まるで待機しているみたいだ。ある夜ベッドに入って二人でうとうとしているとき、クレアは夫に入院先で何人かの女の患者がフェラチオについて語り合っていたことを話した。夫がそういう話が好きだろうと思ったからだ。スチュアートはその話を喜ぶ。そして彼女の腕を撫でる。みんなうまくいくよ、と彼は言う。これから先、何もかも変化して、俺たちもうまくいくさ。彼は昇進し、給料もだいぶ上がった。彼女専用の二台目の車も買った。ステーション・ワゴンだ。これからは今のことだけを考えて生きるのだ。本当に久しぶりにやっと一息つくことができたよ、と彼は言う。暗闇の中で腕をさすりつづける……彼はその後もあいかわらずボウリングやトランプ遊びをしている。三人の友だちと釣りにも行く。
その夜、三つのことが起こった。まずディーンが学校で友達から父親が川で死体を発見したことを聞いてきたのだ。彼はそれについて知りたがった。
スチュアートはほとんどの部分を省略して手短に説明した。うん、そうなんだ、お父さんが三人の友達と一緒に釣りをしているときに死体を見つけたんだ。
「どんな死体?」とディーンは訊ねる。「女の子だったの?」
「うん、女の子だよ。女の人さ。それで保安官を呼んだんだ」スチュアートは私を見る。
「保安官、なんて言った?」とディーンが訊ねる。
「あとのことはこちらが引き受けるってさ」
「どんな風だった? ぞっとした?」
「そのへんでおしまい」と私は言う。「お皿を洗ったらもう行きなさい」
「でもさ、どんな風だったの?」となおもディーンは訊ねる。「聞きたいよ」
「言うことがきけないの?」と私はいう。「言うことがきけないの、ディーン? ディーン!」この子を揺さぶってやりたい。泣き出すまで揺さぶってやりたい。
「お母さんに言われたとおりにしなさい」とスチュアートが静かに言う。「ただの死体さ。べつに話すようなことはなにもないよ」
テーブルを片付けているとき、スチュアートが私の後ろに立って腕に手を触れた。彼の指は焼けるように熱かった。私はぎくっとして皿を落としそうになった。
「どうしたっていうんだよ」と彼は言って手を下ろす。「なあ、クレア、いったいどうしたんだ?」
「びっくりしちゃったのよ」と私は言う。
「そこことを言ってるんだよ。手を触れるたびに君がびっくりしてとびあがるなんて変だと思わないか」彼は私の前に立ってかすかな笑いを浮かべ、私の目をのぞきこむ。そして片手で私の脇腹を抱く。もう片方の手は私のあいている手をとってズボンの前に押しつける。
「やめてよ、スチュアート」私が手をひっこめると、彼は私から離れ、指をパチンと鳴らした。
「そうかい」と彼は言う。「それなら好きなようにしてればいいさ。でもな、よく覚えとけよ」
「何を覚えておくの?」と私は間髪を入れず訊ねる。私はじっと息をつめて彼を見る。
彼は肩をすくめる。「なんでもないよ」と彼は言う。
二つめの出来事が起こったのはその夜二人でテレビを見ていたときだ。彼は革のリクライニング椅子に座り、私はカウチに座って膝に毛布をかけ、雑誌を眺めている。テレビの音を除けば家はしんとしていた。番組に突然アナウンスの声が入り込んだ。殺害された少女の身元が判明しました、詳細は十一時のニュースでお伝えします。
我々は顔を見合わせる。少し間を置いて彼は立ち上がり、寝酒でもつくってくるよと言う。君は?
「いらない」と私は言う。
「べつに一人で飲むさ」と彼は言う。「ちょっと訊いてみただけだよ」
彼はなんとなく傷ついたみたいにみえた。私は目をそらせる。悪いなとも思うけれど、またそれと同時に腹立たしくもあるのだ。
彼はずいぶん長いあいだ台所にいた。しかしニュースが始まると同時に、飲み物を手に戻ってきた。
最初にアナウンサーは四人の地元の釣り人が死体をみつけた話を繰り返した。それから画面に少女の写ったハイスクールの卒業写真が出る。髪は黒く丸顔で、ふっくらした唇に笑みが浮かんでいる。次に少女の両親が遺体確認のために葬儀所に入るフィルムが映し出される。困惑したような、悲しみに打たれたような様子で二人は歩道を葬儀所の入口の階段まで重い足どりで歩いて行く。黒い服を着た男が入り口に立ってドアを手で押さえ、二人が来るのを待っている。ほんの一瞬あとに、まるで中に入ったとたんに回れ右して出てきたみたいに、遺体安置所を出る夫婦の姿が映し出された。女はハンカチで顔を覆うようにして泣き濡れていた。男の方は立ち止まってテレビ・レポーターに向かってしゃべった。「あの子です。スーザンです。今は何も言うこともできません。犯行が繰り返されぬように一刻も早く犯人が捕まることを願っています。こんな酷い……」あとはカメラに向かって弱々しい身振りを見せる。それから二人は旧型の車に乗り込み、夕方近くの車の流れの中に消えていった。
少女の名はスーザン・ミラー、とアナウンサーが続ける。私たちの町の北方百二十マイルにあるサミットという町の映画館で切符係として働いていた彼女は、いつものように仕事を終えた。グリーンの最新型の車が映画館の前に停まり、彼女は歩いていってそれに乗り込んだ。まるでその車が来るのを待っていたみたいでした、と目撃者は言った。警察はその車のドライバーは彼女の友達か、あるいは少なくとも顔見知りであったに違いないと推測していた。警察はそのグリーンの車のドライバーを探していた。
スチュアートは咳払いをして椅子にゆったりともたれて酒をすすった。
三つめの出来事はニュースのあとでおこった。スチュアートは体をのばしてあくびをし、私の方を見た。私は立ち上がりカウチで寝るための用意をする。
「何やってるんだ?」と彼はぽかんとした顔で訊ねる。
「眠くないの」と私は彼の視線を避けて言う。「少しここで本でも読んで、眠くなったらそのまま寝ちゃうわ」
私がカウチにシーツを敷くのを彼はじっと見ている。枕をとりにいこうとすると、彼はベッドルームの入り口に立って私を阻む。
「もう一度訊くけど」と彼は言う。「そんなことをして、いったい何をどうしようと君は思っているんだ?」
「今夜は一人にしてほしいの」と私は言う。「私には考える時間が必要なの。それだけよ」
彼はふうっと息をつく。「君のやっていることは間違っていると思う。自分が何をしているのかもう一度よく考えた方がいいぜ」
何も言えない。何を言いたいのか自分でもよくわからないのだ。私はカウチに戻って毛布の端を押し込んでいく。彼はしばらくそれをじっと見ていたが、やがて肩をすくめる。「それなら好きにしろよ。何しようが俺の知ったこっちゃないさ」彼はそう言うと首を掻きながら廊下をすたすたと歩き去る。
スーザン・ミラーの葬儀は明日の午後二時にサミットのパインズ教会で行われると今朝の新聞に書いてある。また警察は彼女がグリーンのシボレーに乗り込むのを目撃した三人から事情を聴取しているらしい。しかし誰も車のナンバーまでは覚えていない。それでも捜査は核心に近づきつつあり、継続してつづけられている。私は椅子に座ったまま新聞を手にしばらく考えごとをし、それから美容院に電話をかけて予約をとる。
私は雑誌を膝にドライヤーをかぶり、ミリーに爪の手入れをしてもらう。
「明日、お葬式に出るの」以前はその美容院で働いていた女の子についてちょっと話をしたあとで、私はそう言う。
ミリーは頭を上げて私をちらっと見て、それからマニキュアに戻る。「それは御不幸ですわね。ミセス・ケーン。ご愁傷様です」
「亡くなったのは若い娘さんなの」と私は言う。
「それが一番辛いですね。私の姉も私が子供のころに死んだんですけど、そのことはまだ忘れることができませんもの。どなたがお亡くなりになったんですか?」と少しあとで彼女は言う。
「娘さん。それほど親しくしてたわけでもなかったんだけど、それでもやっぱりねえ」
「そうですよね。本当にお気の毒ですわ。でもお葬式に合うようにセット致しますのでおまかせ下さい。こういうのはいかがかしら?」
「そうね……それでいいわ。ねえ、ミリー、あなた誰か他の人になりたいと思ったことある? それとも誰でもなくなってしまいたいとか、無に、一切の無になってしまいたいとか、そういうの」
彼女は私の顔を見る。「そんな風に思ったことってないみたいですわ、ええ。だって私が誰か他の人になったら、私は今度の自分のことが好きになれないかもしれないし」彼女は私の指を持ったまま少し何かを考えているようだった。。「わかりませんわ、どうなんでしょう……じゃあ、そちらの手を貸していただけますか、ミス・ケーン」
その夜十一時、私はまたカウチに寝支度をした。こんどはスチュアートは何も言わなかった。私をじっと見て、唇の裏で舌を丸め、それから廊下を歩いてベッドルームに消える。夜中に目が覚める。風が門扉を垣根にばたんばたんと叩きつけているのが聞こえる。目がさえてしまうのが嫌だったので、私はずっと横になって目を閉じている。でも結局は起きあがり、枕を持って廊下に出る。ベッドルームにが明かりがこうこうと灯り、スチュアートは仰向けになって口をぽかんと開け、大きな寝息をたてている。私はディーンの部屋に行って、そのわきにもぐりこむ。彼は眠りながらも私の場所をあけてくれる。私はしばらくそこに横になっていて、それからディーンの髪を頬にあてるように彼を抱く。
「どうしたの、ママ?」と彼が訊ねる。
「いいからおやすみなさい。大丈夫、なんでもないのよ」
スチュアートの目覚ましの音で私は起き、彼が髭を剃っているあいだにコーヒーを入れ、朝食の用意をする。
彼はタオルを裸の肩にかけて様子をうかがうように台所の戸口に現れる。
「コーヒーはできているわ」と私は言う。「卵もすぐにできるから」
彼は肯く。
私はディーンを起こし、三人で朝食をとる。スチュアートは何か言いたそうな様子でちらりちらりと私を見る。しかしそのたびに私はディーンに向かってミルクはもういいかとか、トーストはいらないかとか、話しかける。
「あとで電話するよ」とスチュアートは出ぎわに言う。
「今日は家にはいないと思うわ」と私は急いで言う。「やらなくちゃいけないことがいっぱいあるし、実のところ夕食までに帰れないかもしれないの」
「うん、いいよ」そしてブリーフケースを持つ手を移しかえる。「今晩は外で食事でもしないか? どう?」彼はじっと私を見ている。彼は死んだ女の子のことなんてもうすっかり忘れているのだ。「おい……大丈夫かい?」
私は彼のネクタイをなおし、それからだらんと手を下ろす。彼は私に出がけのキスをしようとする。私は身を引く。「じゃあ、まあ気をつけてな」と彼はあきらめて言う。そして振り向いて、車まで歩いて行く。
私は丁寧に服を選ぶ。もう何年もかぶったことのない帽子をかぶり。鏡の前に立つ。それから帽子をとり、薄く化粧をする。そしてディーンに置き手紙を書く。
ディーン、お母さんはご用があってかえりがおそくなります。お父さんかお母さんがかえってくるまで、おうちかおにわにいるようにしてください。
LOVE
私は「LOVE」という文句をもう一度眺め、そこにアンダーラインを引く。手紙を書きながら「BACK YARD」という言葉が一語なのか二語なのかを自分が知らないことに気づいた。そんなことこれまでに考えたこともなかった。私は少し考えてからあいだに線を引き、それを二語にわけた。
私はガソリン・スタンドに寄ってガソリンを入れサミットの方角を聞いた。ルイスが給油ホースを入れて、ゆっくりと窓ガラスを拭きはじめるあいだ、バリー、四十歳になる口髭をはやした機械工が便所から出てきてフロント・フェンダーに寄りかかる。
「サミットねえ」バリーは私を眺め、口髭の両側を指で撫でながらそう言う。「サミットにいくうまい道なんてないですよ、ケーンさん。片道二時間から二時間半はかかりますな。山も超えるしね。女の人にはかなりしんどいですぜ。サミット? またなんだってサミットになんか行くんです?」
「用事があるのよ」居心地の悪い声で私は言う。ルイスは別の車の方に行ってしまった。
「うん、そうだな、向こうであんまり時間をとらないんだったら」と彼は言って親指を湾の方に突き出す身振りをする。「あたしが運転していって、連れて帰ってきてあげますよ。道がなにせよくないからね。いや道路じたいはいいんだけど、カーブとかそういうもんが多いんですよ」
「ありがとう。でも大丈夫よ」彼はフェンダーに寄りかかっている。バッグを開けるときに彼の視線を感じる。
バリーはクレジット・カードを受けとる。「夜は運転しちゃだめですよ」と彼は言う。「さっきも言ったようにあまり道がよくないですからね。そりゃ私だってこの車なら大丈夫だって太鼓判押しますよ。この車のことはよく知ってますから。でもねパンクしたりするってこともありますからね。念には念を入れてタイヤを調べといた方がよさそうだな」彼はフロント・タイヤを靴でこんこんとこづく。「ホイストに乗っけてみます。なに、すぐに済みますよ」
「いや、いいの、結構よ。本当に時間がないの。タイヤなら大丈夫みたいよ」
「すぐすみます」と彼は言う。「念には念を入れときましょう」
「いいのよ。いいの! タイヤなら大丈夫。もう行かなくちゃ。ねえ、バリー……」
「なんです?」
「もう行かなくちゃ」
私は何かにサインする。彼は領収書だとかカードだとかスタンプだとかをわたしてくれる。私は全部バッグに仕舞う。「お気をつけて」と彼は言う。「さようなら」
道路の車の列が切れるのを待つあいだに私は後ろを振り向く。彼はこちらをじっと見ている。私は目を閉じ、そして開ける。彼は手を振っている。
私は最初の信号で曲がり、それからもう一度まがり、ハイウェイに出るまでまっすぐ走る。「サミットまで一一七マイル」という標識が見える。十時三十分。暖かな朝だ。
ハイウェイは町の外縁に沿ってぐるっと曲がっている。それから田園地帯を、オート麦やてんさいの畑やりんご園を抜ける。あちこちに牧草地が広がり、牛の小さな群れが草を食んでいる。それから風景ががらりと変化してしまう。農耕地はどんどんまばらになり、家は小屋のようなものへと変わっていく。木材の集積所が果樹園にとってかわる。突然車は山地に入る。右手のずっと下方にナッチーズ川の流れがちらっと見えた。
まもなく緑色のピックアップ・トラックが後方に姿を現し、何マイルかのあいだずっと後についていた。私はは追い抜いてくれないかと思ってスピードを落としたり、スピードを上げたりするのだが、どうもタイミングが合わない。私は指が痛くなるまでハンドルを固く握りしめる。道路が見晴らしのきく長い直線に入ったとき、彼は私を抜いたが、しばらく横に並んで走っていた。髪をクール・カットにして青いワークシャツを着た三十代前半の男だ。我々は顔を見合わせる。それから男は手を振り、二度ホーンを鳴らし、それから追い抜いていく。
私はスピードを落とし、適当な場所――路肩から突き出た未舗装の道――に車を入れ、エンジンを切る。林の下の方から川の音が聞こえる。道は前方の林に吸い込まれている。それからピックアップ・トラックの戻ってくる音が聞こえる。
トラックが後ろに停まるのと同時に私は車のエンジンを入れる。ドアをロックし、ドアの窓ガラスを全部閉める。ギアを入れるとき、顔と腕に汗が吹きだす。でも車を動かそうにも道はふさがれている。
「大丈夫かい?」と男は言って車に近づく。「やあ。どうしたね?」彼は窓をコンコンと叩く。「大丈夫?」彼はドアに両腕をもたせかけ、顔を窓に近づける。
私は彼をじっと見る。言葉が出てこない。
「追い抜いたあとでスピードを落としたんだけどさ」と彼は言う。「バックミラーにおたくの車が映んないもんだから、二分くらい車を停めて待ったんだ。それでもまだ来ないもんで戻って確認したほうがいいと思ったのさ。大丈夫なの? なんで車のなかに閉じ籠もってるんだよ?」
私は首を振る。
「なあ、窓開けなよ。具合わるいんじゃないの? え? 女の人がさ、こんな山の中うろうろするのはまずいよ」彼は首を振り、ハイウェイに目をやり、またこちらを見る。「な、だから窓開けなって。いいだろ? こんなんじゃ話もできないよ」
「お願い。もう行かなきゃいけないの」
「ドアを開けなって」とまるで聞こえなかったみたいに彼は言った。「とにかく窓だけでも下ろしなよ。窒息しちゃうぜ」彼は私の乳房と脚をみる。スカートが膝の上までまくれあがっている。彼の目は私の脚をじろじろと見ている。でも私はじっとしている。動くのが怖いのだ。
「私は窒息したいのよ」と私は言う。「わからない? 私はいま窒息している最中なの」
「まったく何だってんだ?」と男は言ってドアから離れる。彼は背中を向けてトラックに戻る。それからサイドミラーに彼がまたこちらに来るのが映る。私は目を閉じる。
「サミットまでついていってやるとか、そういうのも嫌なんだね? 俺はべつにいいんだぜ。今朝はわりにゆっくりできるからさ」と彼は言う。
私はまた首を振る。
彼はちょっとためらってから肩をすくめる。「まあ好きにしなよ」と彼は言う。「お好きに」
私は彼がハイウェイに出るのを待ってバックする。彼はギアを変え、ゆっくりと遠ざかっていく。バックミラーで私の姿を見ながら。私は路肩に車を停め、ハンドルに顔を伏せる。
棺は閉じられ、花で覆われている。私が教会のいちばん後ろ近くの席に腰を下ろすとまもなくオルガンが鳴りはじめる。人々がぞろぞろ入ってきて、席を探しはじめる。中年の人々、もっと上の人々もいる。しかしほとんどは二十代前半か、それよりももっと若い人々だ。スーツにネクタイ、ジャケットにスラックス、黒いドレスに革手袋といった格好の彼らはどことなくぎこちない。ベルボトムのズボンと黄色い半袖シャツを着た少年が私の隣に座り、唇を噛みしめる。教会の片側の扉が開き、私はふと顔をあげる。ほんの少しのあいだ、駐車場が草地のように見える。でもやがて太陽の光が車の窓にキラッと反射する。親族がひとかたまりになって入場し、カーテンで仕切られた側面の離れた一画に入る。彼らが腰を下ろすときに椅子がきしんだ音を立てる。二、三分あとでダークスーツに身を包んだ痩せた金髪の男が立って、頭を垂れて下さいと我々に言う。彼はまず我々、生者のための短い祈りの言葉を口にし、それが終わるとみんなで亡きスーザン・ミラーのために黙祷を捧げましょう、と言う。私は目を閉じ、テレビや新聞の写真で見た彼女の顔を思い浮かべる。彼女が映画館を出てグリーンのシボレーに乗り込むところが見える。それから彼女が川を流されている光景を想像する。裸の死体が岩にうちつけられ、枝にひっかかり、ぐるぐると回り漂う。髪は流れのままに揺れる。それから川面に突き出た木の枝が彼女の手や髪を捕らえ、そこに留める。やがて四人の男がやってきて彼女をじろじろと眺める。酔っぱらった男(スチュアート?)が彼女の手首をつかむ。ここにいる人たちの中にそのことを知っている人はいるのかしら? もしそれを知ったら、みんなどう思うだろう? 私はまわりの人々の顔を見回す。これらの物事、これらの事件、これらの顔によって作りあげられるべき関係のようなものがあるはずだ。私はそれを見つけようとするが、おかげで頭が痛む。
牧師はスーザン・ミラーの四つの徳について語った。快活さ、美しさ、優雅さ、そして熱意である。閉じたカーテンの後ろで誰かが咳払いし、誰かがすすり泣く。オルガンの演奏が始まる。葬式が終わる。
参列者の列にまじって私はゆっくりと棺の前をとおりすぎる。そして正面の階段に出て、眩しく暑い午後の太陽を浴びる。びっこを引いて階段を下りていた私の前の中年の女性が歩道に下りるとあたりをぐるっと見回す。私と目が合う。「捕まりましたよ」と彼女は言う。「それでどうなるというものでもありませんがね。とにかく今朝犯人が捕まったんです。ここに来る前にラジオで聴いたんです。町の人間ですよ。やっぱり思ったとおり長髪族の仕業でしたねえ」私たちは焼けた舗道を何歩か歩く。みんなもう車を発進させている。私は手をのばしてパーキング・メーターにつかまる。磨きあげられた車のフードやフェンダーが太陽の光を照りかえしている。頭がふらふらする。「その夜、彼女と関係をもったことは認めたんだけど、殺してはいないって言ってるんですよ」彼女は鼻を鳴らした。「でもたぶん保護観察つきで釈放ってことになるんじゃないかしら」
「共犯者がいたのかもしれませんわ」と私は言う。「ちゃんと調べるべきだわ。誰かをかばっているんじゃないかしら。兄弟とか友達とか」
「あの娘は小さいころから知ってるんですよ」と彼女は話しつづける。唇が震えている。「よくうちに遊びに来て、来るとクッキーを焼いてやりました。そしてテレビの前でそのクッキーを食べさせてやったんですよ」彼女は顔を背けて頭を振る。涙の粒が彼女の頬をつたって落ちる。
3
スチュアートはテーブルの椅子に座っている。彼の前には酒のグラスが置いてある。彼の目は赤く、一瞬私は彼が泣いていたんじゃないかと思う。彼は私を見て何も言わない。突然ディーンの身に何かが起こったんじゃないかという考えが頭にひらめく。気が動転する。
「どこなの?」と私は言う。「ディーンはどこ?」
「外だよ」と彼は言う。
「スチュアート、私すごく怖いの、すごく怖いのよ」と私はドアに寄りかかって言う。
「何が怖いんだい、クレア。言ってごらん。助けたあげられるかもしれないよ。俺は君の力になりたいんだ。言ってごらん。だってそれが夫の役目じゃないか」
「うまく言えないの」と私は言う。「私はただ怖いのよ。私はつまり、つまり、つまり……」
彼は私から目を離さないようにしながらグラスをぐいと飲み干して立ち上がる。「君に必要なものはわかってるさ。俺が君のお医者になってやるよ、な? さあ、楽にして」彼は私の腰に腕をまわし、もう一方の手で私の上着のボタンをはずし、それからブラウスにかかった。「まずやるべきことをやろうな」と彼は冗談めかして言う。
「今はだめ、お願い」と私は言う。
「今はだめ、お願い」と夫はからかって言う。「何がお願いだよ」と。そして私の後ろにまわって腕をぎゅっと体にまきつけ、もう一方の手をブラジャーの中に滑りこませる。
「やめて、やめて、やめて」と私は言って、彼の足の先を踏みつける。
私は上にかかえあげられ、それから崩れ落ちる。私は床に座り込んだまま夫を見上げる。首が痛い。スカートは膝の上までまくれあがっている。彼はかがみこむようにして言う「お前なんかくたばっちまえ。お前のおまんこなんか腐り落ちてしまえばいいんだ」そして一度だけすすりあげる。きっと押さえ切れないのだ。自分を押さえることもできないのだ。彼は居間に行ってしまう。私は突然彼のことを気の毒だと思う。
昨夜夫は家に帰らなかった。
今朝花が届く。赤と黄の菊だ。私がコーヒーを飲んでいると玄関のベルが鳴る。
「ケーンさんですか?」と若い男が言う。花の入ったボックスを持っている。
私は肯いて、ローブの襟を首まで合わせる。
「名前は言わなくても誰だかわかるよ、と御注文なさった方はおっしゃっておられました」男の子は喉のところが開いている私のローブに目をやる。彼は両足を開き、階段のいちばん上の段に踏んばって立っている。「それではどうも有難うございました」と彼は言う。
少しあとで電話のベルが鳴る。「やあ、元気?」とスチュアートが言う。「今日は早く帰る。愛してるよ。聞こえたかい? 愛してるよ。悪かったと思ってる。仲なおりしようよ。じゃあね。今ちょっと忙しいからさ」
花を花瓶に入れ、食堂のテーブルのまんなかに置く。それから私は自分の荷物を客用のベッドルームに運び込む。
昨夜、一二時ごろ、スチュアートは私の部屋のドアの鍵を壊した。たぶん彼はそうしようと思えばできるんだということを私に示したかったのだろう。その証拠にドアがばたんと開いたときにも、彼はべつになにもしない。下着姿のまま驚いたようなきまりの悪いような顔をしてそこに突っ立っているだけだ。怒りの表情が彼の顔からすべり落ちるように消えていく。彼はゆっくりとドアを閉める。少し間があって、製氷皿の氷をとる音が台所から聞こえる。
今日スチュアートから電話があったとき、私はベッドの中にいた。二、三日母に家に来てもらうことにしたよ、と彼は言う。私はそのことについて少し考えてから、彼がまだしゃべりつづけている途中で電話を切る。しかしほどなく、私は彼の会社に電話をかける。彼がやっと電話に出る。「べつにそれでかまわないわよ、スチュアート」と私は言う。「本当にかまわないの、べつになんだっていいのよ」
「愛してるよ」と彼は言う。
彼は何かべつのことをしゃべっている。私ははそれを聞きながらゆっくりと肯く。私は眠い。それから私ははっと目を覚ます。そして言う。「ねえ、スチュアート、わかって。彼女はまだほんの子供だったのよ」
好き…
夜、メンマ、抹茶、麻婆豆腐、揚げたてコロッケ、鯵の干物、古典落語、猫
嫌い…
朝、レバ刺し、らっきょう、玉子かけご飯、満員電車、安倍晋三