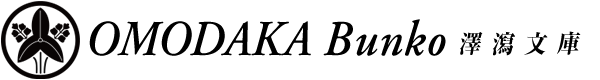この「サマー・スティールヘッド」は僕がブラインドタッチの練習として入力したものです。
どうせ入力するなら、練習用アプリの面白くない文章よりも好きな作家の文章の方が身が入るし、楽しいだろうと始めてみました。
そして、まあ、どうせ入力してテキストデータになったのだから、置いておこうかと…
そして、そして、ついでなのでちょと覚え書きも…
レイモンド・カーヴァーを練習用に選んだのはまったくの偶然。
数日前にいつもの中央図書館に行った時に、なんとなく手に取ったカーヴァーの本の表紙がこんな和田誠さんのイラストで、ぱらぱらめくってたら「サマー・スティールヘッド」なんていう短編のタイトルがあって、速攻で借りて帰ってきたんだ。
で、「そうだ、そうだ。せっかくだから、これをブラインドタッチの教材にしてみよう」と思い立った次第です。
好きな作家の文章を打ち込むのは思っていた通り、楽しい作業でした。ミスタッチの連続で思い通りにいかず、イライラしっぱなしだったけど、レイモンド・カーヴァーの世界観を感じながらそれを文書化していくのは、読むのとはまた違った楽しさがありましたね。
データ形式の違いでここでは反映されていないけど、「釣り竿」と打って、「フライ・ロッド」とルビをふったりした時には、思わずにやけてしまったものです。
「サマー・スティールヘッド」を「夏にじます」と訳すことに、釣師として、中でもフライマンの一人ととして、違和感というか抵抗感を感じることが無いではないけど、訳者の村上春樹はフライマンではないので、そこはいたしかたのないところでしょう。
センテンスはあくまで短く、形容詞も少なめ。良質のハードボイルド小説のような潔い文体で『僕』の物語は進んでいく。レイモンド・カーヴァーの世界観そのものといった物語。
そして、読後になんとなく物悲しいのもレイモンド・カーヴァーらしい物語です。
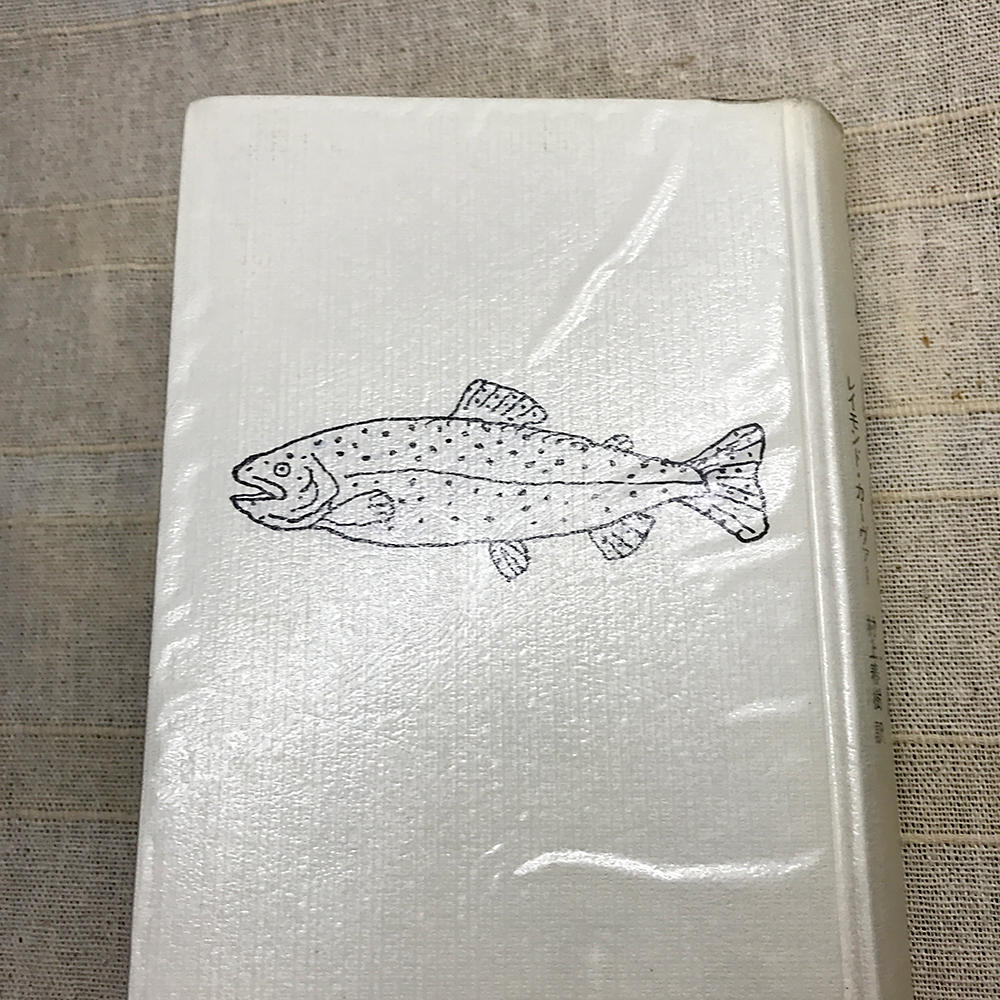
+++++++++++++++++++++++++++++
サマー・スティールヘッド
Raymond Carver
台所から二人の声が聞こえてきた。何を言っているのかは聞き取れなかったけれど、とにかく二人は言い争っていた。でもやがて静かになり、母さんが泣きはじめた。僕はジョージを肘でつっついた。ジョージが目を覚まして二人のところに行って何か言い、それで彼らがうしろめたく思って喧嘩をやめるんじゃないかと考えたのだ。でもジョージときたら相変わらずの脳足りんで、足をどんどんと蹴って、大声をあげた。
「なにしやがる、畜生め」と弟は言った。「言いつけてやるからな」
「このうすのろの馬鹿」と僕は言った。「お前脳味噌ってものがないのか。二人が喧嘩して、ママは泣いてるんだぞ。ほら、聞いてみろ」
弟は枕から頭を上げて、耳を澄ませた。「知ったこっちゃねえや」と彼は言って壁の方にごろんと寝がえりを打ち、そのまま眠ってしまった。ジョージときたら国宝級の脳足りんなのだ。
そのあとで僕は父さんがバスに乗るために家を出ていく音を聞いた。彼は玄関のドアをばたんを閉めた。母さんは前に僕らに言ったことがあった。お父さんは家族をばらばらにしてしまうつもりなのよ、と。僕はそんな話を聞きたくなかった。
それから少しして、母さんが学校に行くために僕らを起こした。母さんの声はなんだか変だった。ちょっとそんな気がした。おなかの具合がおかしいんだよと僕は言った。それは十月の第一週で、僕はそれまで一日も学校を休んだことはなかった。だから母さんも文句は言えなかった。母さんは僕の顔を見た。でも母さんは何か別のことを考えているみたいだった。ジョージは目を覚まして、話を聞いていた。体の動かし方で、僕には奴が起きていることがわかった。なりゆき次第ですぐに行動に移れるように奴はじっと待ち構えているのだ。
「わかったわ」と母さんは言って首を振った。「しかたないわね。じゃあ家でじっとしていなさい。でもテレビは見ちゃ駄目よ。わかった?」
ジョージが体を起こした。「ぼくだって病気だよ」とジョージは母さんに言った。「頭が痛いんだ。兄ちゃんが一晩中蹴ったりつついたりするもんだから、全然寝られなかったんだよ」
「よしなさい!」と母さんは言った。「あなたは学校に行くのよ、ジョージ! ここに残しておいたら、お兄さんとずっと喧嘩してるだけじゃない。さあ、早く起きて支度をしなさい。早くするのよ。朝っぱらからもう一戦交えたくなんかないのよ」
ジョージは母さんが部屋から出ていくのを待っていた。それからベッドの足もとの方から這い出た。「この野郎」と奴は言って、僕の布団を全部はぎとってしまった。そしてさっさとバスルームの中に逃げ込んでしまった。
「殺してやるからな」と僕は言った。母さんに聞こえないくらいの小さな声で。
ジョージが学校に行ってしまうまで、僕はじっとベッドの中にいた。母さんが仕事に行く用意にかかると、僕はカウチに寝支度をしてもらえないだろうかと頼んでみた。勉強がしたいんだよ、と僕は言った。コーヒー・テーブルの上には誕生日にもらったエドガー・ライス・バローズの本と、社会科の教科書が載っていた。でも僕は本なんて読む気にはなれなかった。早く母さんが出ていってくれたらテレビが見られるのになと思っていた。
母さんがトイレットの水を流した。
僕はもう一刻も待てなかった。僕は音を出さないようにテレビの画像をつけた。僕は台所に行って母さんが置きっぱなしにした煙草の箱の中から三本を抜き出し、カップボードのなかに入れ、それからカウチに戻って『火星のプリンス』を読み始めた。母さんはやってきてテレビがついているのを目にとめたが、何もいわなかった。僕は本を開いていた。母さんは鏡の前に立って髪をちょっと整え、それから台所に行った。母さんが出ていくとき、僕はまた本に目を戻した。
「もう遅刻しそう。気をつけてね」彼女はテレビのことは何も言わないことにしたみたいだった。昨夜母さんはこう言ったのだ。「心穏やかに」仕事に出かけるということがどういうことなのか、私にはもううまく思い出せないわと。
「料理なんか作らないでちょうだいね。ガスをつけるような必要はありませんからね。おなかが減ったら冷蔵庫にツナが入ってるわよ」母さんは僕の顔を見た。「胃の具合が悪いのなら、何も食べない方がいいと思うけれど、とにかくガスをつけたりする必要はないのよ。わかった? お薬を飲みなさい、坊や。そうすれば夜までには元気になると思うから。あるいは私たちはみんな、夜までには元気になっているかもね」
母さんは戸口に立ってノブをまわした。彼女はもっと他に何かを言いたそうに見えた。白いブラウスに幅広の黒いベルト、黒いスカートという格好だった。母さんはあるときにはそれを「衣装」と呼び、あるときには「制服」と呼んだ。僕が覚えている限りでは、それはいつもクローゼットに吊るされているか、物干しロープにかかっているか、夜中に手洗いされているか、あるいは台所でアイロンをかけられているか、そのどれかだった。
母さんは水曜から日曜まで働いていた。
「いってらっしゃい、母さん」
母さんが車のエンジンをかけ、それを温め終えるのを待っていた。そして車が道路に出ていく音に耳を澄ませた。それから僕は立ち上がって、テレビの音を大きくし、煙草を取りにいった。僕は一本吸い、医者と看護婦の出て来る番組を見ながらマスターベーションをやった。それから別のチャンネルに変えた。そしてテレビを消した。テレビを見るような気分でもなかったのだ。
僕はタース・ターカスが緑の女と恋に落ちる章を読み終えた。結局、彼女はその翌朝には、嫉妬深い義兄の手で首をはねられてしまうことになるのだが。それを読むのはかれこれもう五回めだった。それから僕は両親のベッドルームに行って、いろいろと物色してみた。とくに何かを探すのではなく、まあコンドームでもあればなというくらいの気持ちだった。でもこれまでもどれだけ丹念に探しても、そいつはちっともみつからなかったのだ。一度僕は引き出しの奥にワセリンの瓶をみつけた。それはあれに何か関係のあるものだろうと僕は思った。でも何に使うのかはわからなかった。僕はラベルを読んで何か手がかりを得ようと思った。そのワセリンで人は何をするのか、あるいはまたどのようにしてそれを使用するのか、そういうことを知りたかったのだ。でもそんなことはどこにも書かれていなかった。表のラベルには「純正ペトローリアム・ゼリー」と書いてあるだけだった。でもそんな表示を読んだだけで、僕は硬くなってしまった。裏のラベルには「育児室の必需品」とあった。僕は育児室――ブランコと滑り台と砂場とジャングル・ジム――と、ベッドの中で男女が行うことのあいだにどんな相関関係があるのだろうかと考えてみた。僕は何度も蓋を開けて中の匂いを嗅ぎ、この前に比べてどれくらい量が減っているかを調べてみた。でも今回は僕は純正ペトローリアム・ゼリーをパスした。つまり引き出しの中にまだその瓶があることを確かめるだけにしたのだ。とくに何かがみつかるとは期待しなかったけれど、僕はいくつか引き出しを開けてみた。ベッドの下も覗いてみた。どこにも何もなかった。両親が食品雑貨を買うためのお金を貯めておく、クローゼットの中の広口瓶も覗いてみた。小銭はまるでなかった。五ドルと一ドル札が一枚ずつ入っていただけだった。それがなくなったら、彼らはたぶん気づくだろう。それから僕は服を着替えてパーチ・クリークまで歩いて行こうと思った。鱒釣りのシーズンはまだ一週間かそこら残っていたけれど、釣りをする人間はもうほとんどいなかった。みんな今は、鹿と雉の猟が解禁になるのに備えて英気を養っているのだ。
僕は古い服を出した。普通の靴下の上にウールの靴下を重ねてはいた。そして時間をかけてブーツの紐を結んだ。ツナのサンドイッチを二つ作り、三段重ねのピーナッツバター・クラッカーをいくつか作った。水筒に水を入れ、ベルトにハンティング・ナイフと水筒を取り付けた。玄関を出る時に、僕は書き置きを残しておこうと思った。僕はこう書いた。「具合が良くなったので、パーチー・クリークに行ってきます。すぐに戻る。R。三時十五分」三時十五分にはまだ四時間ある。そしてジョージが学校から帰ってくるのは、その十五分後だ。家を出る前に僕はサンドイッチを一個食べ、ミルクを一杯飲んだ。
外の空気は格別だった。季節は秋だった。でも夜を別にすれば、まだ寒くはなかった。夜になると果樹園では霜よけのいぶし器の火を焚いた。そのせいで、朝目をさますと鼻の中に黒い輪っかのようなものがついていた。でもそれについて誰も文句を言わなかった。いぶし器を焚くと若い梨が凍らずにすむ、だからそれはしょうがないのだとみんなは言った。
パーチ・クリークに行くには、まず僕らの家の前の通りをいちばん先まで行く。道はそこで一六番通りに突き当たる。一六番通りを左に折れ、丘を登り、墓地の前を通り過ぎ、ずっと下って中華料理店のあるレノックスまで行く。そこの十字路から空港が見える。そしてパーチ・クリークは空港の下の方にある。一六番通りはその十字路を境にして、ヴュー・ロードに変わる。ヴュー・ロードを少し進むと橋に出る。道路の両側は果樹園になっている。果樹園の横を通りかかる時に、雉たちが畝を走っているのを見かけることがある。でもそこで猟をすることはできない。マツォスという名のギリシャ人に撃たれるかもしれないからだ。全部で歩いて四〇分くらいの道のりだと思う。
一六番通りを半分くらい歩いたところで、赤い車に乗った女の人が僕の行く手の路肩に車を停めた。彼女は助手席の窓を下ろして、乗っていくかと僕に尋ねた。痩せた女で、口のまわりに小さな吹き出物があった。髪はカーラーに巻きつけられていた。でもけっこうな美人だった。茶色のセーターの下のおっぱいが目立った。
「さぼりなの?」
「ええ、まあ」
「乗っていく?」
僕は頷いた。
「じゃあ早く乗りなさい。私、けっこう急いでるのよ」
僕は釣り竿とびくをバックシートの上に置いた。バックシートにも床にもメルズ・マーケットの食料品の袋がどっさりと置いてあった。僕は何か言わなくちゃなと思って考えた。
「釣りに行くんです」と僕は言った。僕は帽子を取り、座りやすいように水筒を前に回した。そして窓のわきに体を落ち着けた。
「人は見かけによらないものね」と女は言って笑った。そして車を道路にだした。「どこまで行くの。パーチクリークかしら?」
僕はまた頷いた。僕は自分の帽子を見た。それは叔父さんがシアトルにホッケーの試合を見に行ったときにお土産に買ってくれたものだった。それ以上何を言えばいいのか、僕にはわからなかった。僕は窓の外を見ながら頬っぺたをへっこませていた。こういう女に誘われるなんて、まさに夢のとおりだ。そして当然二人はすっかりその気になってしまうのだ。女は家にいらっしゃいよと誘い、そして彼女の家の中のあっちやこっちやで二人はやりまくるのだ。そんなことを考えているうちにまた硬くなってきた。僕は膝の上に帽子を移し、目を閉じた。そして野球のことを考えようとした。
「私、ずっとみんなに言ってるの。そのうちに釣りを始めるからって」と女が言った。「すごくリラックスするって言うから。私、神経質な人間なのよ」
僕は目を開けた。車は十字路のところで停まっていた。僕はこう言いたかった。「本当にそんなに忙しいんですか? 今朝から始めてみればいいじゃないですか」と。でも僕は彼女の顔を見るのが怖かった。
「ここまででいいかしら。私、ここで曲がらなくてはならないのよ。ごめんね。今日はちょっと先を急いでいるものだから」と女は言った。
「いいです。ここでかまいません」僕は自分の荷物を車から下ろした。僕は帽子をかぶり、それをまた脱いで言った。「さようなら。どうも有り難う。たぶん来年の夏になったら」と僕は言いかけたが、そのあとを続けられなかった。
「ああ、釣りのこと? ええ、きっとそうするわ」と彼女は言って、指を二本立てて振った。よく女の人がやるように。
僕は歩き始めた。自分が口にするべきだった台詞を頭の中で繰り返しながら。僕はいろんな台詞をいっぱい思いつけた。なのにいざとなるとどうして駄目なんだろう? 僕は釣り竿でひゅうっと風を切って、二、三度何事かを叫んだ。まず手始めに僕はやるべきことは、お昼御飯でも一緒にいかがですかと誘うことだったのだ。僕の家には誰もいない。そして突然僕らは、僕のベッドルームの布団の中にいる。セーターを着たままでもかまわないかと彼女は訊いて、かまわないよと僕は答える。彼女はズボンもはいたままだ。かまわないよと僕は言う。僕はべつにいいんだ。
バイパー・カブが僕の頭をかすめるようにして、飛行場に降下していった。あと数フィートで橋だった。水音も耳に届いた。僕は急いで土手に下りてジッパーを下ろし、クリークに向かってばっちりと五フィート飛ばした。こいつはたぶん新記録だ。僕は一休みして、サンドイッチの残りのもう一個とピーナッツバター・クラッカーを食べた。水筒の水を半分飲んだ。それから僕は釣りにとりかかった。
どこから始めようかと僕は考えてみた。ここに越してきてから三年のあいだ、僕はずっとここで釣りをしてきた。父さんはよく僕とジョージを車に乗せてここに連れてきて、僕らのことをじっと待っていたものだった。煙草を吹かし、餌を付け、針が何かに引っかかると新しいのを結びつけてくれた。僕らはいつも橋のところから始め、だんだんと下流に移動していった。そしていつも二匹か三匹釣り上げた。ときには、シーズン初めのことだが、僕らは規定量いっぱいまで釣り上げることもあった。僕は針をセットすると、まず橋の下で何度かキャスティングしてみた。
僕はところどころで土手の下とか、大きな岩の後ろなんかに針を落としてみた。でも反応はなかった。水が静かで、黄色い葉が底に溜まったところでは、目を凝らすと、何匹かのザリガニがその醜い鋏をうえにかざして這っている姿が見えた。幾重にも重なった茂みからは、鶉たちがぱっと飛び立った。棒きれを投げると、一羽の雄の雉がバタバタバタという音を立てておよそ十フィートばかり飛び上がり、おかげで僕はあやうく釣り竿を取り落としてしまうところだった。
クリークの流れは穏やかで、幅もそんなになかった。たいていどこでも長靴の中に水を入れることなく向こう岸まで渡ることができた。僕は牛の足跡でいっぱいの牧草地を横切り、大きなパイプから水が溢れ出しているところまでやってきた。そのパイプの下に小さな穴が穿たれていることを知っていたから、僕はちゃんと注意を払った。釣り糸を垂らせるくらい近くまで来ると、僕は両膝をついた。針が水面に触れるか触れないかで、魚の食いつく手応えがあった。でも僕は逃してしまった。そいつが針を引っかけたままぐいぐいと引くのが手に感じられた。でもそいつはそのまま行ってしまった。糸がはねるようにひゅうと戻ってきた。僕は新しい鮭の卵を付けて何度かキャスティングしてみた。でも一度けちのついたものはやっぱり駄目だった。
僕は土手を上っていって、柱に「立ち入り禁止」という札のかかった金網の下をくぐり抜けて上にあがった。滑走路のひとつはそこから始まっていた。僕は歩みをとめて、舗装の割れ目に咲いている何本かの花を見た。飛行機のタイヤが舗装された地面に着地する地点を見ることができる。花のまわりには、そこいらじゅうに油まじりのタイヤ跡が残っていた。そこを越すと、またクリークにでる。僕は途中、ちょこちょこと釣りをしながら、その深みのところまで行った。この先にはもう行けないなと僕は思った。三年前にここに来たとき、水は土手のいちばん上までに達していて、轟々と音を立てていた。水の流れは早すぎて、とても釣りなんてできなかった。でも今の水嵩は土手からおおよそ六フィート下にあった。底がほとんど見えないくらい深いたまりの土手には短い瀬があって、水は泡立ち、跳ね上がりながら底を越えた。少し下っていくと、水底はなだらかな坂のように上にあがってきて、まるでなにごともなかったみたいにまた浅くなった。この前ここに来たとき、僕は十インチほどもあるのを二匹釣り上げ、その倍はあろうかという大物を逃してしまった。僕がその話をすると、そいつはサマー・スティールヘッド(夏にじます)だな、と父さんは言った。水嵩がある早春のあいだにその魚はこっちまで上ってくるんだ。でもその大部分は水嵩の減る前に川に戻ってしまう。
僕は釣り糸にもうふたつ針を付け、歯でぎゅっと結んだ。それから餌として生の鮭の卵を付け、水が浅瀬から落ちてたまりになっているところに糸を落とした。僕は水の流れがそれを運んでいくにまかせた。おもりが岩にとんとんと当たる感触が感じられた。魚が食いついたときとは違うとんとんだった。それから先の方がぴんと張り、流れが卵をたまりの端の方の目に見えるところに運んでいった。
こんなところまで来て何も獲物がないなんて冗談じゃないなと僕は思った。今回は僕はたっぷりと糸を引っぱり出し、もう一度キャスティングしてみた。僕はフライ・ロッドを大きな枝の上に載せ、最後から二本めの煙草に火をつけた。そして谷間を見上げ、あの女のことを考えはじめた。女が食料品を運ぶのを手伝ってくれと言って、僕らは彼女の家まで行くのだ。彼女の夫は海外に行っている。僕が手を触れると、彼女は身を震わせはじめる。カウチの上で二人でフレンチ・キスをしていると、彼女はバスルームに行きたいと言う。僕は彼女のあとについていく。彼女がパンツを下ろして便器に腰かけるのが見えた。僕はとち狂ってしまう。そして彼女は僕を手招きする。僕がズボンのジッパーを外そうとしたちょうどそのときに、クリークの方でぽちゃんと音がするのが聞こえた。そちらに目をやると、僕のフライ・ロッドの先が小刻みに揺れているのが見えた。
魚はすごく大きいというのではなかったし、抵抗らしい抵抗もしなかった。でも僕はできるだけ長くそいつを泳がせておいた。そいつは横腹を見せて、下の方の流れに横たわってしまった。それがどういう魚なのか、僕にはわからなかった。見慣れない魚だった。僕は糸を引いて、そいつを土手の草の上に引っぱり上げた。魚はそこでくねくねと体をよじらせながらじっと宙を見ていた。それは鱒だった。でも体の色は緑色だった。そんなのを見たのは始めてだった。腹が緑色で、黒い鱒の班があった。頭も緑で、まるで緑色の胃袋みたいに見えた。それは藻のような緑だった。まるで長い間藻に包みこまれていたせいで、その色が体に染み込んでしまったみたいだった。身もよくついていた。どうしてもっと元気に抵抗しなかったんだろうと僕は不思議に思った。この魚、大丈夫なのかな、とも思った。僕はまだしばらく魚を見ていた。それから僕は魚を苦痛から解放してやった。
僕は草を何本か引き抜き、それをびくの中に入れ、魚をその草の上に置いた。
あと何度か僕は糸を投げた。それから、もう二時か三時にはなっているだろうなと思った。そろそろ橋の方に向かった方がいいだろう。橋の下で少し釣りをしてから、家に帰ろう。そして夜になるまで、あの女のことを考えるのはよそうと思った。でも僕はすぐに、その夜に硬くなることを想像しただけで硬くなった。それから僕はあれをやりすぎるのをやめなくちゃと思った。家族がみんな出かけた一ヵ月ほど前の土曜日の夜、それをやった直後に聖書を手にとって誓ったのだ。こんなこともう二度とやりませんと。でも僕は聖書に精液をつけてしまった。そしてその聖なる誓いも一日か二日しかもたなかった。もう一度一人きりになったら、それでおしまいだった。
帰り道では釣りをしなかった。橋に着くと、草むらの中に自転車が一台あった。見回すと、ジョージくらいの大きさの男の子が土手を駆けているのが見えた。僕はそれと同じ方角に向かって歩きはじめた。すると彼は向きを変えて、川に目を向けながら僕の方にやってきた。「おい、どうしたんだよ!」とぼくはさけんだ。「何かあったのか?」でも僕の声は彼の耳には届いていないようだった。彼の釣り竿と釣りのバッグが土手の上に置いてあるのが見えた。僕は自分の荷物を下に落とした。そして男の子の方に駆けていった。彼は鼠とか、何かそういうものに似ていた。歯が前に出ていて、腕はがりがりで、裾のほつれたサイズの小さすぎる長袖のシャツを着ていた。
「ねえ、あんな大きな魚を見たのは本当に生まれて初めてだよ!」と彼は大きな声で言った。
「ほら、ここだよ。見てごらんよ! ここだよ、ここにいる!」
その子の指した方を見たとたん、僕の心臓は飛び上がってしまった。
そいつは僕の腕くらいの長さがあったのだ。
「あああ、すごい、見てよ」と少年は言った。
僕はじっとそいつを見ていた。そいつは水の上に張り出した大枝の影に身を休めていた。
「すげえ」と僕は魚に向かって言った。「お前、いったいどこから来たんだ?」
「どうしたらいいだろう?」とその男の子は言った。「銃でも持ってりゃな」
「あいつを捕まえるんだ」と僕は言った。「なんてでかいんだ。まったく。とにかく浅瀬に追い込むんだよ」
「じやあ手伝ってくれるの? 一緒にやろう」と男の子はいった。
その大きな魚は下流に向けて数フィート、ゆっくりと泳いでいった。そしてその澄んだ水の中に留まって、ゆっくりと尾を動かしていた。
「オーケー、それでどうするの?」
「僕は上流に行って、クリークを下ってくる。そして奴を追い立てる」と僕は言った。「お前は早瀬に立っているんだ。あいつがそこを通り抜けようとしたら、足で蹴とばして死ぬほど脅かしてやるんだ。そして何がなんでもあいつを土手の上に放りあげるんだ。そしたら奴をしっかり捕まえてしがみついてるんだよ」
「わかった。ああ畜生、あれを見てよ! ねえ、あいつどこかに行っちまうよ。どこに行くんだろう?」と少年は大声で叫んだ。
魚はクリークをまた上流に向かって進み、土手の近くで止まった。「どこにも行きゃしないさ。行ける場所もないんだ。見たか? あいつは死ぬほど怯えてるんだ。あいつは俺たちがここにいることを知っている。どこか逃げ場はないものかと思って、その辺をただぐるぐると回ってるだけなんだ。ほら、また止まっただろう。どこにも逃げ場がないんだ。そしてそのことは自分でもわかってるんだ。あいつは俺たちが自分のことを追い詰めようとしてることもわかってるんだ。それが生半可なことじゃないこともな。俺は上流に行って、あいつを脅して追い立てる。ここを抜けようとしたら、しっかりと押えこむんだぞ」
「銃があったらなあ」と男の子は言った。「あいつを仕留められるのにな」
僕は少し上流に行った。そしてクリークに入って、ばしゃばしゃと歩いて下流に向かった。僕は自分の進んでいくちょっと前方に目を向けていた。突然魚が土手から飛び出してきて、僕の前で大きな濁った渦を巻いて右に旋回した。そしてものすごい勢いで下流に向かった。
「そっちに行くぞ!」と僕は怒鳴った。
「おーい、いいか、そっちに行ったぞ!」しかし魚は浅瀬の手前でくるりと向きを変えて、こっちの方に戻ってきた。僕は水しぶきをあげ、大声を出した。するとそいつはまた向きを転じた。「さあ、行ったぞ! 捕まえろ、捕まえるんだ! 行ったからな!」
でもその脳足りんは棍棒を手にしていた。どうしようもない間抜けだ。そして魚が浅瀬にさしかかったとき、言われたとおりに足で蹴って追うのではなく、棒を持って襲いかかったのだ。魚は向きをかえ、半狂乱になって、体を横倒しにして浅瀬を越えてしまった。抜けてしまったのだ。その間抜けの餓鬼は魚に襲いかかろうとして、ばったり転んでしまった。
彼はぐしょ濡れになって土手の上に這い上がった。「あいつを叩いたよ」と少年は叫んだ。「傷ついたと思うよ。魚に触ったんだ。でもしっかり捕まえられなかった」
「触ったわけなんかないだろうが!」と僕は息を切らせて言った。こけていい気味だと僕は思った。「近くにも寄れなかったじゃないか、このうすのろ。棍棒なんか持っていったいどういうつもりなんだ。蹴飛ばせって言ったろうが。あいつは今ごろはもう一マイルも向こうに行っちまってるよ」僕は唾を吐こうとした。そして頭を振った。「まったくもう。とにかく魚を捕まえられなかった。もう捕まえることはできないかもしれない」
「冗談じゃないぜ。僕はあいつを叩いたんだよ!」と少年は金切り声を上げた。「見てなかったのかい? 僕はあいつを叩いて、体にだって手をかけたんだ。あんた近くで見てたわけじゃないだろう。それにだいたいあの魚は誰のものなんだよ?」少年は僕の顔を見た。水がズボンの上を垂れて、靴の上にぼたぼた落ちていた。
僕はそれ以上は何も言わなかった。でも僕はそれについて考えてみた。そして肩をすくめた。「まあ、いいさ。魚は俺たち二人のものだろう。今度はきっちりと捕まえようじゃないか。お互いもう、どじはなしだぜ」と僕は言った。
僕らは水の中を歩いて下流に向かった。僕の長靴の中には水は入っていた。でも男の子の方は首までぐしょ濡れだった。彼はがたがた音を立てないように、出っ歯で唇をぎゅっと噛みしめていた。
魚は早瀬の下の流れにもいなかった。そしてその次の流れの中にもその姿は見当たらなかった。僕らは顔を見合わせた。そして魚はもうずっと下流の方にまで逃げて、深い穴を見つけたのかもしれないと思った。でもそのときそいつが土手の脇で身をくねらせた。その尾を振って、なんと土を水の中にどぼんと落としたのだ。そしてまた前進を始めた。魚はもうひとつ浅瀬を越えた。その大きな尾びれは水の上に突き出ていた。僕はそいつが土手の脇をゆっくりと泳ぎ、そして止まるのを見た。尾の半分は水の上に突き出て、流れに対して位置を保持するためにゆっくりと振られていた。
「見えるか?」と僕は言った。男の子はそっちに目をやった。僕は彼の手を取り、その指をそっちの方向に向けてやった。「ほら、あそこだよ。いいか、よく聞けよ。俺はあの土手のあいだの小さな流れのところまで行く。言ってること、わかるか? 俺が合図するまでここでじっとしているんだぞ。合図したらあるき出すんだ。いいか、もしあいつが回れ右しても、今度は通り抜けさせるんじゃないぞ」
「わかったよ」と男の子は言って、例の歯で唇をぎゅっと噛みしめた。「今度こそ捕まえてやるぞ」と彼は言った。その顔は寒さで震えあがっていた。
僕は土手の上にあがり、音を立てないように注意して歩いた。そしてまた土手をおりて。水の中にそっと足を踏み入れた。でもそのでかい畜生はどこにも見当たらなかった。僕の心臓は引っくり返ってしまいそうだった。そいつはもうどこかに行ってしまったのかもしてないと思ったのだ。もう少し下流まで行くと、そこには穴があり、そうなると僕らはもう奴を捕まえることができなくなってしまう。
「あいつはまだそこにいるのか?」と僕は怒鳴った。僕はじっと息をこらした。
男の子が手を振った。
「よし、いいぞ!」と僕はまた怒鳴った。
「行くよ!」と男の子も怒鳴りかえした。
僕の手ががくがくと震えていた。クリークの川幅は三フィートほどで、両岸は土の堤になっていた。水は浅いがその流れは速かった。男の子は下流に向かって進んでいた。膝まで水につかり、前方に向かって石を投げていた。ばしゃばしゃとしぶきを立てて、叫び声をあげていた。
「そっちに行ったよ!」男の子は両腕を振って言った。魚の姿が見えた。そいつはまっすぐ僕の方に向かってやってきた。奴は僕の姿を見て向きを変えようとした。でもそうするには遅すぎた。僕は膝をついて、冷たい水の中に手を突っ込んだ。僕は両手と両腕を使ってそいつを抱えあげ、ちょっとずつ上に上にと持ち上げ、水の中から放り出した。僕と魚は組み合ったまま土手の上に倒れ込んだ。僕は奴をずっとシャツの上に押さえこんでいた。魚は身をくねらせ、のたうちまわっていた。でも僕はやっとのことで。そのつるつる滑る脇腹にそって鰓のところまで両手を持っていくことができた。僕は片手をその中に入れて口のところまで突っ込み、顎をぐっと押さえこんだ。さあ捕まえたぞ、と僕は思った。魚はそれでもまだびちびちと跳ねて、押さえつけているのはひと苦労だった。でもとにかく僕はこいつを捕まえたのだし、もう何があろうと放したりはしない。
「捕まえたぞ!」と男の子は叫びながら、水しぶきを立ててやってきた。「わあ、捕まえたぞ。すごいや、こいつは! やったね。ねえ、僕にも持たせてよ、それ!」と彼は叫んだ。
「まず息の根を止めるんだ」と僕は言った。僕はもう片方の手を喉に這わせた。そしてなんとかそいつの歯に注意しながら、頭を思い切り後ろに引いた。ぼきっという重い手応えがあった。魚はぶるぶるっと長く、ゆっくりと震え、そして静かになった。僕は魚を土手の上に横たえ、二人でその姿を眺めた。長さは少く見積もっても二フィートはあった。ひどく痩せてはいたが、それでも僕がこれまでに釣り上げたどんな魚より大きかった。僕はもう一度その顎を手に取った。
「ねえちょっと」とその子は言いかけたが、僕がやろうとしていることを見て取ると、それ以上はもう何も言わなかった。僕は血を洗い流してから、魚をもう一度土手の上に戻した。
「その魚、何がなんでもお父さんに見せなくちゃ」と男の子は言った。
僕らはぐしょ濡れになってぶるぶる震えていた。僕らは魚を見ながら、その体に触りつづけていた。大きな口をこじ開けて、歯並びを触ってみた。魚の体の両側には傷がついていた。二五セント硬貨くらいの大きさの、ぷっくりと腫れ上がった白いみみずばれがあった。頭の外側の目のまわりと、吻のところには、刻み目のような傷がいくつかあった。それは岩にぶつかったり格闘したりしたときについたものなのだろうと僕は推測した。でもそいつは本当に痩せていた。体長と比べると、あまりにも痩せすぎていた。体の両脇のピンクの線だってもうほとんど見えなくなっていた。白くてぴちぴちしているはずの腹は、灰色でたるんでいた。でも、それにしたってこいつは大物だと僕は思った。
「もうそろそろ引きあげようや」と僕は言った。そして丘の上に浮かんだ雲を見た。太陽はそこに沈みかけていた。「家に帰らなくちゃ」
「そうだね。僕も帰らなくちゃ。体が凍ってしまいそうだよ」と男の子は言った。「ねえ、僕がその魚を担いでいきたいな」
「何か棒を持ってこよう。そいつを口から通して二人で担いでいけばいい」と僕はいった。
男の子が棒を見つけてきた。僕らはそれを鰓のなかに突っ込み、魚の体が棒の真ん中にくるようにした。そして二人で両端を持ち、魚がゆらゆらと揺れる姿を見ながら帰路についた。
「こいつをどうするんだよ?」と男の子が尋ねた。
「どうしたものかな」と僕は言った。「こいつを捕まえたのは俺だよな」と僕は言った。
「二人で捕まえたんじゃないか。それに最初にみつけたのは僕だぜ」
「それはたしかにそうだ」と僕は言った。「投げ銭か何かそういうのできめようか」僕は空いた方の手で小銭を探した。でも僕は一銭ももっていなかった。それにもし僕が負けでもしたら、いったいどうするんだ。
でもいずれにせよ、男の子は首を振った。「投げ銭なんて嫌だね」
「オーケー、嫌なら嫌でいいさ」僕はその男の子を見た。髪の毛は上に突っ立って、唇は白くなっていた。必要とあらば腕ずくで取り上げることはできる。でも僕としては喧嘩はしたくなかった。
僕らは荷物を置きっぱなしにしたところまで来て、それぞれの荷物を片手で広いあげた。どちらも棒の端を離さなかった。それから僕らは彼が自転車を置いたところまで歩いた。僕は男の子が何かしようとしたときのために、棒をぎゅっと固く握りしめていた。
それから僕はひとつの案を思いついた。「半分に分けようじゃないか」と僕は言った。
「どういうことだよ?」と男の子は言った。彼の歯はまたがちがちと音を立てていた。彼が棒をぎゅっと握りしめるのが感じられた。
「半分に分けるんだよ。俺はナイフを持っている。真ん中から切って、半分ずつ持って帰るんだ。よくわかんないけどさ、それがいいんじゃないかな」
彼は髪の毛を一筋引っぱりながら、魚を見た。「あんたのナイフを使うのかい?」
「お前もってるのか?」と僕は尋ねた。
男の子は首を振った。
「じゃあ決まりだ」と僕は言った。
僕は棒を抜き取って、男の子の自転車の脇の草の上に魚を置いた。そしてナイフを取り出した。分割する線の位置を計っているときに、飛行機が一機滑走路を移動してきた。「ここでいいか?」と僕は言った。男の子は肯いた。飛行機は大きな音を立てて滑走路を走り、機首を上げて僕らの頭の真上を飛んでいった。僕は魚を切りにかかった。はらわたの部分まで来ると、僕は魚を引っくり返して、中のものを残らずとっぱらった。そして腹の皮一枚だけでかろうじて体がひとつに繋がっているというところまで、僕は切っていった。僕は両手に魚の半分ずつを持って、感触を確かめてから、それをふたつにちぎった。
僕は尾の方を男のこに渡した。
「嫌だね」と彼は首を横に振りながら言った。「そっちの半分の方がいいよ」
僕は言った、「そんなのどっちだって同じだろうよ。なあ、いいか、いつまでもそんな文句ばかり言ってると、俺だって頭に来ちゃうぜ」
「来たってかまうもんか」と男の子は言った。「もしどっちだって同じなんなら、僕は頭の方をもらうよ、だってどっちだって同じなんだろう?」
「どっちだって同じさ」と僕は言った。「でも俺はこっちをもらう。切ったのは俺なんだからな」
「僕はそっちが欲しい」と男の子は言った。「僕がそいつを最初にみつけたんだ」
「誰のナイフを使ったんだ?」と僕は言った。
「尻尾の方なんて僕は嫌だね」と男の子は言った。
僕はまわりを見渡した。道路には車の姿はみえなかった。釣り人もいない。ブーンという飛行機の低い唸りが聞こえた。太陽は沈もうとしていた。僕の体はすっかり冷え込んでいた。男の子もがたがたと激しく震えながらそこに突っ立っていた。
「いい考えがある」と僕は言った。僕はびくを開けて、彼に鱒を見せた。「ほら緑色の奴がいるだろう。緑色の奴なんて、俺も見たの初めてだよ。それでだな、どっちかが頭の方を取ったら、もうひとりは尻尾の方の半分とこの緑の奴を取るんだ。それで公平じゃないかな」
男の子はその緑の鱒を見て、びくから取り出し、手に取った。そして半分に切られた魚をしげしげと見た。
「そうだね」と彼は言った。「オーケー、それでいいや。あんたがそっちの方を取ればいいよ。僕は身が多い方がいい」
「お好きに」と僕は言った。「今綺麗に洗うよ。お前、家はどっちの方なんだ?」
「アーサー・アヴェニュー」彼は緑の鱒と半分を汚らしいキャンバスの袋に入れた。
「どうしてさ?」
「どの辺だよ。野球場のあたりか?」と僕は訊いた。
「ああ。でもどうしてって尋ねたんだよ」男の子はびくついているみたいだった。
「俺、その近くに住んでるんだ」と僕は言った。「だから一緒に自転車に乗せていってもらえないかと思ってさ。かわりばんこにこげばいい。俺、モクも持ってるんだ。一緒に吸えるぜ。水がかかってなきゃいいんだけどな」
でも男の子は「寒くて死にそうだよ」と言っただけだった。
僕は自分の分の魚をクリークの水で洗った。僕はそのでかい頭を水につけて、口を開けた。水は口から入って、残された体の端っこから出ていった。
「凍えてしまいそうだ」と男の子は言った。
ジョージが通りの向こう端で自転車に乗っているのが見えた。ジョージは僕には気がつかなかった。僕は長靴を脱ぐために裏口に回った。肩から下げていたびくをはずして蓋が開けられるようにし、笑みを浮かべながら家の中に堂々と凱旋する用意をした。
彼らの声が聞こえたので、僕は窓の中を覗きこんでみた。二人はテーブルに就いていた。台所は煙でいっぱいだった。それはレンジの上のフライパンから上がっている煙だった。でも二人ともそんなことには構いもしなかった。
「俺がお前に言ってるのは絶対的な真実だ」と父さんは言った。「子供たちがどこまで知ってるか? 今にわかるさ」
母さんはいった、「私には何もわかりゃしないわ。そんなこと考えるくらいなら、子供たちはいっそのこと死んでしまった方がいいわよ」
父さんは言った、「おい、なんてことを言うんだ。言葉を慎め!」
母さんは泣きはじめた。父さんは煙草を灰皿にぎゅっと押しつけ、立ち上がった。
「おいエドナ、フライパンが煙あげてるじゃないか」と父さんは言った。
母さんはフライパンを見た。椅子を後ろに引き、フライパンの柄をつかむと、それを流しの上の壁に向かって投げつけた。
父さんは言った、「お前、気でも狂ったのか? なんてことするんだ、まったく」彼は布巾を取って、フライパンからこぼれたものを拭きはじめた。
僕は裏のドアを開けた。そして顔に笑みを浮かべた。僕は言った、「ねえ、パーチ・クリークで何を釣り上げたと思う? ほら、見てよ。これ見てごらんよ。僕がとったんだぜ」
僕の脚は震えていた。立っているのがやっとだった。僕はびくを母さんの前に差し出した。母さんはやっと中を覗き込んだ。「わあ、何よこれはいったい! 蛇じゃない! おねがい、どこかにやって。吐きそうだわ」
「外に持っていくんだ!」と父さんが叫んだ。「お母さんの言ったことが聞こえないのか。外に持っていけったら」
僕は言った、「だってお父さん、これ見てよ」
父さんは言った、「そんなもの見たくない」
僕は言った、「パーチ・クリークでとれた馬鹿でかいサマー・スティルヘッドだよ。見てよ。ちょっとしたものだと思わない? もうばけものだよ。僕は死にものぐるいでクリークじゅう追っ掛けまわしたんだ」僕の声は興奮して震えていた。でも僕は喋るのをやめられなかった。「この他にももう一匹とったんだ」と僕は早口で喋りつづけた。「緑色の奴なんだよ。ほんとに。緑色だぜ! 緑の鱒なんて見たことある?」
父さんはびくの中を除きこんだ。そして口をぽかんと開けた。
彼は大声を上げた。「こんなもの、どこかに持っていけ。お前、頭がいかれたんじゃないのか? 台所にこんなもの持ち込む奴があるか。さっさとごみ箱に捨ててくるんだよ!」
僕は外に出た。そしてびくの中を覗きこんだ。そこにあるものはポーチの光の下では銀色に見えた。そこにあるものでびくはいっぱいになっていた。
僕はそいつを持ち上げた。僕はそいつをじっと持っていた。僕はそいつの半分をじっと手に持っていた。
好き…
夜、メンマ、抹茶、麻婆豆腐、揚げたてコロッケ、鯵の干物、古典落語、猫
嫌い…
朝、レバ刺し、らっきょう、玉子かけご飯、満員電車、安倍晋三