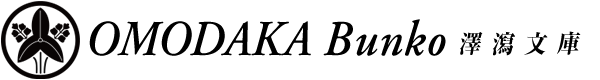「アラスカに何があるというのか?」も、レイモンド・カーヴァーの短編集『頼むから静かにしてくれ』に収められてる作品です。
ブラインドタッチの練習にテキスト入力しました。
この作品はある意味現代の日本の作家としては、成立し得ない作品です。
作品の内容とは関係のないことだけど、特に最近の監視社会、密告社会、警察国家、そして全体主義国家へと突き進むこの国では、成立しないでしょう。
馬鹿なネトウヨが「犯罪者」だと大騒ぎし、それにマスコミも載っかって大騒ぎし、したり顔のお上が許さないでしょう。
先進国と呼ばれる多くの国では今や、医療用の大麻は解禁の動きが当たり前となり、国によっては個人で嗜好として使用するのも解禁となっているというのに…
作品としては、他愛のない内容の小品です。
ちょっと田舎町に住む、一組の夫婦(たぶん)が仕事を終え、夕食も終えた後、近所に住む友人夫婦(たぶん)の家に行き、みんなで大麻を吸って、やくたいもない与太話で大笑いするというだけの話です。
そこには、強い思想性も社会批判も、体制批判もプロパガンダもない。
大麻を吸うための吸引具と、吸引後の他愛のないおしゃべりが、ちょっとのリアリズムで描かれているだけです。
大麻を吸って、馬鹿笑いして、アメリカンなジャンクフードの馬鹿食いという、見なれた者にとっては見なれた場面の展開です。
そしてそこに、レイモンド・カーヴァーの最も得意な、なんだかよくわからないけど酸っぱいようなもの。薄らさみしいような何かが付加されています。
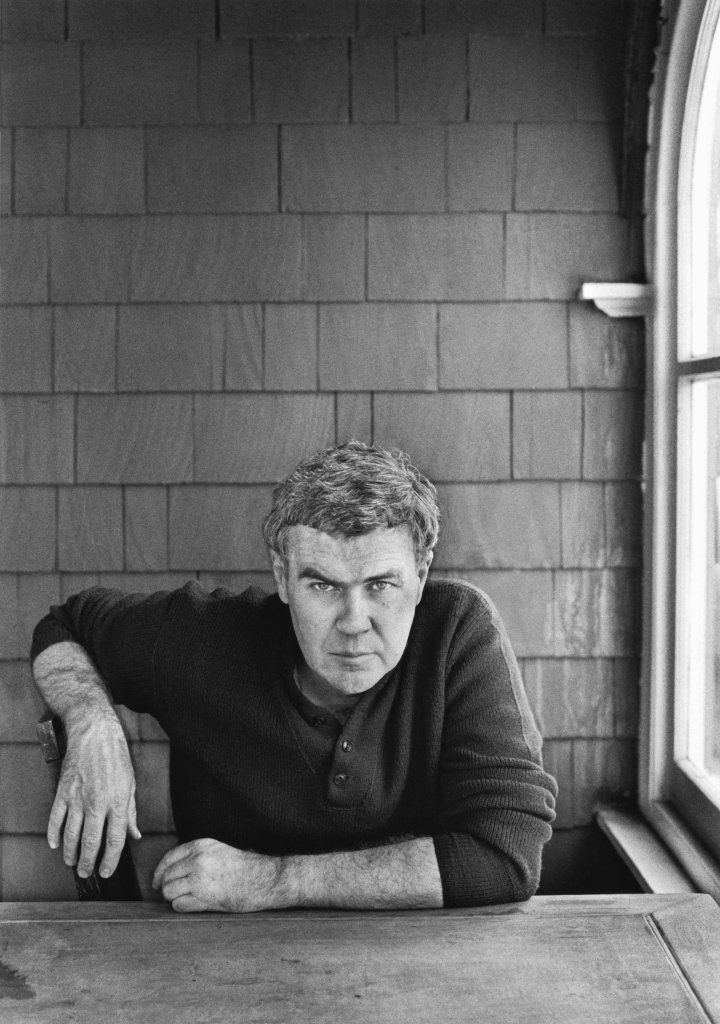
ところで、大麻が効いてきてよろしくなっている状態を、訳者の村上春樹は『ラリってる』と表現しているんだけど、ちょっとこれは違和感があるなぁ…
僕の周りでは『ラリってる』というのは、どちらかといえばシンナーとか、ブロンとかの薬品・薬物系で、本人もわけわからなくなっているような状態を指し示す言葉でしたね。
大麻やキノコの場合には『飛んでる』『ぶっ飛んでる』、または『ハイ』と言って、
なんとなく、薬物系とナチュラル系とでは言葉も使い分けていました。
村上春樹もボストン(だったか?)で、大学の客員教授として暮らしていた時には、近所の大学仲間などから「ちょっとイイのが手に入ったから、一服いっしょにどう?」なんて度々誘われて、よろしくやっていたと随筆に書いていたので、経験者と言うよりはこの国の警察やマスコミが言うところの「常習者」だったんだよね。
なのでこの辺のニュアンスは正確に書き分けて欲しかった気もするけど、「大麻は好きだし、大騒ぎするほどのことじゃないけど、リスクの大きさが違いすぎるので日本では絶対にやらない」とも書いていたので、細かな国内事情には疎かったのかもしれない。
まあ、いづれにしても瑣末なことです。
++++++++++++++++++++++++++
アラスカに何があるというのか?
Raymond Carver
カールは三時に仕事を終えた。彼は職場を離れると、車でアパートの近くの靴屋に行った。そしてストゥールに足を載せて、店員にワークブーツの紐をほどかせた。
「履き心地のいいやつが欲しいんだ」とカールは言った。「普段履きのやつが」
「承知いたしました」と店員は言った。
店員は三組の靴を出してきた。カールはソフトなベージュの靴にすると言った。それを履くと、彼の足はゆったりとして、元気がよくなったように感じられた。彼は金を払い、ワークブーツを入れた箱を小脇に抱えた。そして歩きながら下を向いて、自分の新しい靴を眺めた。車を運転して帰宅するとき、彼は自分の足がペダルからペダルへさっさと闊達に動くのを感じた。
「あら、新しい靴を買ったのね」とメアリが言った。「みせてよ」
「どう、気に入った?」とカールは訊いた。
「色はあまり気に入らないけど、でも履き心地よさそうじゃない。靴も買いどきだったしね」
彼は新しい靴をまた眺めた。「風呂に入らなくちゃな」と彼は言った。
「私たち早めにお夕食を食べなくちゃ」と彼女は言った。「ヘレンとジャックに招待されてるの。ヘレンはジャックの誕生日に水パイプをプレゼントしたんだけど、あの人たちそれを試したくてしょうがないのよ」メアリはそう言って彼のほうを見た。「あなたは行くのかまわない?」
「何時に?」
「七時頃」
「かまわないよ」と彼は言った。
彼女はもう一度彼の靴を見て、頬っぺたをすぼませた。「じゃ、お風呂に入ったら」と彼女は言った。
カールは湯を出して、靴と服を脱いだ。彼はしばらくバスタブにつかっていたが、やがてブラシを使って爪の中の潤滑用グリースを掃除した。彼は両手を下ろして、それから目の前にかざした。
彼女がバスルームの戸を開けた。「ビールを持ってきてあげたわよ」と彼女はいった。蒸気が彼女のまわりを通りすぎて、居間の方に流れていった。
「もうすぐ上がるよ」と彼は言った。彼はビールを少し飲んだ。
彼女はバスタブの縁に腰を下ろし、手を彼の腿に置いていた。「家がいちばんね」と彼女は言った。
「家がいちばん」と彼も言った。
彼女は腿の濡れた毛の中に手を這わせた。それから彼女はぱちんと手を叩いた。「そうだ、ひとつ言い忘れてた! 今日、私ひとつ面接を受けたんだけど、どうやらそれが上手くいきそうなのよ。仕事がもらえそうなのよ――フェアバンクスで」
「アラスカの?」と彼は訊いた。
彼女は肯いた。「あなたはそのことどう思う?」
「俺はずっとアラスカに行ってみたかったんだ。それはたしかな話しなのか?」
彼女はまた肯いた。「向こうは気に入ったみたいだわ。来週に返事くれるって」
「そいつは上出来だ。タオルを取ってくれないか。そろそろ出るよ」
「じゃあテーブルの用意をするわね」と彼女は言った。
彼の指の先と爪先はすっかり白くなって皺がよっていた。彼はゆっくりと体を拭いて、新しい服に着替え、買ったばかりの靴を履いた。それから髪をとかしてキッチンに行った。彼女がテーブルに料理を並べているあいだに、もう一本ビールを飲んだ。
「私たちはクリームソーダを少しと、何か軽いスナックを持っていくって言ってあるの」と彼女は言った。「どこかのお店に寄って買っていかなくちゃ」
「クリームソーダとスナックね。了解」と彼は言った。
夕食が終わると、かれは食卓のかたづけを手伝った。それから二人は車でスーパーに行って、クリームソーダとポテトチップとコーンチップとオニオン味のスナック・クラッカーを買った。レジのところで、彼はユーノー・バーをひとつかみ追加した。
「ああ、そうね」と彼女はそれを見て言った。
二人は家に戻り、車を停めた。それから同じブロックにあるヘレンとジャックの家まで歩いた。
ヘレンがドアを開けた。カールは袋をダイニング・ルームのテーブルの上に置いた。メアリはロッキング・チェアに腰を下ろし、くんくんを匂いを嗅いだ。
「どうやら私たち遅れちゃったわね、カール」と彼女は言った。「二人はもう先に始めたみたいよ」
ヘレンは笑った。「ジャックが帰ってきたときに一服やったのよ。水パイプの方はまだ初めてないからご安心を。あなたたちが来るのを待っていたんだから」彼女は部屋の真ん中に立って、二人の顔を見ながらにやにやしていた。「さあ、何を買ってきてくれたのかしらね」と彼女は言った。「わあ、すごい。このコーンチップを早速今いただいちゃおうかしら。あなたたちはいかが?」
「夕食を済ませてきたばかりなんだ」とカールが言った。「もうちょっとあとにするよ」水の音が止まり、ジャックがバスルームの中で口笛を吹いているのがカールに聞こえた。
「うちにはポプシクルが何本かとM&Mがあるわ」とヘレンは言った。彼女はテーブルの脇に立って、ポテトチップに袋の中に手を突っ込んでいた。「ジャックがいつの日にかシャワーから出てきたら、水パイプを始めると思うわ」彼女はスナック・クラッカーの箱を開け、ひとつを口に入れた。「うん、これすごくおいしいじゃない」と彼女は言った。
「エミリー・ポスト女史がこういうのを見たら何と言うかしらね」とメアリが言った。
ヘレンは笑って首を振った。
ジャックがバスルームから出てきた。「よう、よく来たね。やあ、カール。何がそんなにおかしいんだい?」彼はそう言ってにやっと笑った。「笑い声が聞こえたけど」
「ヘレンのことを笑ってたのよ」とメアリが言った。
「ヘレンが笑ってたんだよ」とカールが言った。
「おかしい女でねえ」とジャックは言った。「おや、こいつは美味しそうだなあ。なあどう、クリームソーダ飲むかい? 俺はパイプの支度をするからさ」
「私はいただくわ」とメアリが言った。「あなたはどうする、カール?」
「俺もちょっと貰おう」とカールは言った。
「カールは今晩ちょっと御機嫌ななめなのよ」とメアリが言った
「なんでそんなことを言うんだよ?」とカールは言った。彼は彼女の顔を見た。「そんなこと言われたら俺は本当にそうなっちゃうぜ」
「からかっただけじゃない」とメアリは言った。彼女は彼の方に来て、ソファーの隣に腰を下ろした。「ちょっとからかっただけよ、ハニー」
「ようカール、機嫌なおせよ」とジャックが言った。「俺が誕生日のプレゼントに貰ったものを見せてやるよ。なあヘレン、俺がパイプの支度するあいだ、そのクリームソーダの瓶を開けといてくれよ。喉がからからだよ」
ヘレンはチップとクラッカーをコーヒー・テーブルに置いた。それからクリームソーダの瓶とグラスを四つ持ってきた。
「なんだかまるでパーティーみたいだわね」とメアリが言った。
「一日じゅうおなかが減って死にそうってくらいにしとかないと、週に十ポンドは体重が増えちゃうんだから」とヘレンは言った。
「それは言えるわねえ」とメアリが言った。
ジャックが水パイプを手にベッドルームから出てきた。「さあこれだよ、これ」と彼はカールに向かって言って、その水パイプをコーヒー・テーブルの上に置いた。
「こりゃたいしたもんだな」とカールは言った。彼はそれを手に取って、しげしげと眺めた。
「こいつの名前はフーカっていうのよ」とヘレンは言った。「買ったところではそう呼んでいたわ。これは小型のやつなんだけどね、それでもなかなか強力なものなのよ」ヘレンはそう言って笑った。
「どこで手に入れたのよ?」とメアリが訊いた。
「何ですって? ああ、フォース・ストリートにある小さな店よ。知ってるでしょう?」ヘレンはそう言った。
「ええ、知ってる」とメアリは言った。「そのうちに一度行ってみなくちゃね」とメアリは言った。彼女は両手を重ねて、じっとジャックを見た。
「どんな風にやるんだい?」とカールが訊いた。
「ここに葉っぱを入れて、ここに火をつけるんだ」とジャックが言った。「そしてここから吸い込む。すると煙が水の中を通ってくる。それで味も良くなるし、キクんだよ、こいつがまた」
「私もカールのクリスマス・プレゼントに買ってあげようかしら」とメアリが言った。彼女はカールの方を向いてにっこりし、彼の腕に手を触れた。
「俺もひとつ欲しいな」とカールは言った。彼は足をのばして、光の下で新しい靴を眺めた。
「さあ、一服やってみなよ」とジャックは言って、細い一筋の煙を吐き出し、カールの方にチューブを差し出した。「どんなか試してみなよ」
カールはチューブから煙を吸い込み、それを肺の中にとどめ、チューブをヘレンの方に回した。
「メアリが先にやれば」とヘレンは言った。「私はメアリのあとでやる。あなたたちも追いついてちょうだい」
「じゃあお言葉に甘えて」とメアリが言った。彼女はチューブを口にくわえ、勢いよく吸い込んだ。それも二度。カールは彼女の立てた泡を見ていた。
「これすごくいいじゃない」とメアリは言った。そしてチューブをヘレンに回した。
「私たち昨夜これを試してみたのよ」とヘレンは言った。そして大声で笑った。
「こいつ、朝子供たちと一緒に目覚めたとき、まだラリッてたんだぜ」とジャックは言った。彼も笑った。彼はヘレンがチューブを吸うのを見ていた。
「子供たちは元気?」とメアリが尋ねた。
「ああ、元気にしているよ」とジャックは言った。そしてチューブをくわえた。
カールはクリームソーダを一口飲み、パイプの中の泡を見ていた。それは潜水夫のヘルメットから上がってくる泡を思わせた。かれはラグーンと、美しい魚の群れを想像した。
ジャックがチューブを回した。
カールは席を立って、体をのばした。
「どこに行くの、ハニー?」とメアリが訊いた。
「どこにも行かないよ」とカールは言った。彼は腰を下ろし、首を振ってにやっと笑った。「これはこれは」
ヘレンは笑った。
「何がおかしいの?」とずっとあとでカールが尋ねた。
「そんなのわかんない」とヘレンは言った。彼女は目をこすって、また笑いはじめた。そしてメアリとジャックも笑った。
少したってからジャックは水パイプのてっぺんのねじを緩め、チューブのひとつをふううと吹いた。「ときどきチューブが詰まっちゃうんだ」
「君はさっき俺の機嫌が悪いって言ったけど、あれはどういう意味なんだ?」とカールがメアリに尋ねた。
「何ですって?」とメアリが言った。
カールは彼女の顔をじっと見つめ、目を細めた。「君は俺の機嫌が悪いとかなんとか言ったじゃないか。なんであんなこと言ったんだよ?」
「思い出せないわ、それ。でも私には、そういうのちゃんとわかるのよ」と彼女は言った。「でもネガティブな話題は今は持ち出さないでね。わかった?」
「わかった」とカールは言った。「俺が言いたかったのは、どうして君がそんなこと言い出したのかよく理解できないというだけなんだけれどね。もし君がそう言い出すまで俺が落ち込んでいなかったとしたら、君はそう言ったことで俺を落ち込ませることに成功したってことにるね」
「ぴったしカンカン」とメアリは言って、ソファーの腕のところによりかかるようにして、涙が出るまで笑いころげた。
「何、なんだって?」とジャックが言った。彼はカールを見て、それからメアリを見た。「よく聞こえなかったんだけど」とジャックは言った。
「何かこのチップにつけて食べるものを用意しとけばよかったわね」とヘレンが言った。
「クリームソーダはもっとないの?」とジャックが言った。
「俺たち二本買ってきたよ」とカールが言った。
「もう二本とも飲んじゃったのかなあ」とジャックが言った。
「私たち何か飲んだっけ?」とヘレンが言って笑った。「いいえ、私は一本しか栓を抜いてないわよ。一本しか抜いてない、と思う。一本以上栓を抜いた覚えがないのよ」ヘレンはそう言って笑った。
カールはメアリにチューブを回した。彼女は彼の手を取って、そのままの格好でチューブを口にくわえた。彼はずっとあとで彼女の唇の上を煙が漂うのを見た。
「クリームソーダはどう?」とジャックは言った。
メアリとヘレンは笑った。
「どうなの?」とメアリは言った。
「みんなで一杯やるって話じゃなかったっけ」とジャックは言った。彼はメアリの方を見てにこっと笑った。
メアリとヘレンは声を上げて笑った。
「何がおかしいんだよ」とジャックは言った。彼はヘレンを見て、それからメアリを見た。彼は首を振った。「君たちのことはよくわからないね」
「我々はアラスカに行くことになるかもしれない」とカールが言った。
「アラスカだって?」とジャックが言った。「アラスカにいったい何があるんだ。あんなところでいったい何をしようっていうんだ?」
「私たちもどこかに行きたい」とヘレンが言った。
「ここのどこがいけないんだ?」とジャックが言った。「君たち、アラスカでいったい何をやるんだよ? 冗談抜きで知りたいね」
カールはポテトチップを口に入れ、クリームソーダをすすった。「わからないな。なんて言ったっけね?」
ちょっと間をおいてジャックが言った。「アラスカに何があるんだ?」
「わからないよ」とカールは言った。「メアリに訊いてくれよ。メアリなら知ってるからさ。なあメアリ、俺はアラスカでいったい何をやればいいんだろう? あるいは君がどこかで読んだ馬鹿でかいキャベツでも育てるのかな」
「それともカボチャ」とヘレンが言った。「カボチャを作るの」
「そいつは当たるぜ」とジャックは言った。「ハローウィン用にこっちに送るんだ。俺が販売代理店をやってやるよ」
「ジャックが販売代理店をやる」とヘレンは言った。
「そのとおり」とジャックが言った。「俺たちは大もうけできる」
「大金持ちになれる」とメアリが言った。
そのうちにジャックが立ち上がった。「俺はいま何がいちばん美味しいかわかってる。それはクリームソーダだ」とジャックは言った。
メアリとヘレンは笑った。
「お好きに笑えばいいさ」とジャックはにやにやしながら言った。
「誰かクリームソーダを飲みたい人は?」
「何を飲みたいって?」とメアリが言った。
「クリームソーダ」とジャックが言った。
「あなたが立ち上がったところ。まるで何か演説するみたいな感じだった」とメアリが言った。
「そんなこと考えてもみなかった」とジャックが言った。彼は首を振って笑った。そして腰を下ろした。「これはモノがいいな」と彼は言った。
「もっと手に入れておくんだったわ」とヘレンが言った。
「もっと何を?」とメアリが言った。
「もっとお金を」とジャックが言った。
「金はない」とカールが言った。
「袋の中にユーノー・バーが入ってたわよねえ」とヘレンが言った。
「ちょっと買ったよ」とカールが言った。「最後にレジのところでふっと買っちゃたんだ」
「ユーノー・バーはいいな」とジャックが言った。
「クリーミーだし」とメアリが言った。「口の中でとろけるのよ」
「うちにはM&Mとポプシクルがある。もし食べたかったらどうぞ」とジャックが言った。
メアリが言った。「ポプシクルが食べたいな。あなたキッチンに行くことある?」
「ああ、どうせクリームソーダ取りに行くから」とジャックが言った。「それで思い出した。君たちもう一杯どう?」
「持ってくるだけ持ってきて。あとで考えるから」とヘレンが言った。「M&Mも持ってきてね」
「キッチンをこっちに持ってきた方が楽かもしれないな」とジャックが言った。
「私たちが都会に住んでいたときにはみんなこう言っていたわ」とメアリが言った。「朝にキッチンを見れば、前の晩にラリったかどうかわかるって。都会に住んでいたときには、私たちのキッチンは狭かったの」
「狭いキッチンだった」とカールはいった。
「何か食べるものを探してこよう」とジャックが言った。
「一緒に行くわ」とメアリが言った。
カールは二人がキッチンの方に行くのを見ていた。彼はクッションに背をもたせかけ、二人が歩いていくのを見守っていた。それから彼はゆっくりと前かがみになった。彼はめを細くして見た。ジャックがカップボードの棚に手をのばすのが見えた。メアリがジャックの後ろに近寄って、彼の腰に腕を回すのが見えた。
「あなたたち本気なの?」とヘレンが訊いた。
「大真面目な話だよ」とカールは言った。
「アラスカのことよ」とヘレンは言った。
彼は彼女の顔をじっと見た。
「あなた何か言わなかった?」とヘレンが言った。
ジャックとメアリが戻ってきた。ジャックはM&Mの入った大きな袋とクリームソーダの瓶を持ってきた。メアリはオレンジのポプシクルをなめていた。
「誰かサンドイッチ食べたい人はいる?」とヘレンが訊いた。「サンドイッチの材料ならあるんだけど」
「それ、おかしいわね」とメアリが言った。「まずデザートから食べはじめて、それからメイン・コースに行くんだから」
「おかしいなあ」とカールは言った。
「何か気に入らないことでもあるの。ハニー?」とメアリが言った。
「誰かクリームソーダ飲む?」とジャックが言った。「みなさんクリームソーダがありますよ」
カールがグラスを差し出し、ジャックがそれになみなみとクリームソーダを注いだ。カールはグラスをコーヒー・テーブルの上に載せた。でもコーヒー・テーブルにがしゃんとぶつかって、ソーダが彼の靴の上にこぼれ落ちてしまった。
「畜生」とカールは言った。「なんてこった。靴の上にこぼしちまったよ」
「おいヘレン、タオルあるか? カールにタオル持ってきてやれよ」とジャックは言った。
「おニューの靴なのよ」とメアリが言った。「買ったばかりなの」
「履き心地のよさそうな靴よね」とずいぶんあとでヘレンが言った。そしてカールにタオルを渡した。
「私もおなじこと言ったわ」とメアリが言った。
カールは靴を脱いで、タオルで革をごしごしとこすった。
「こりゃもう駄目だな」と彼は言った。「このクリームソーダは全然取れないや」
メアリとジャックとヘレンは笑った。
「新聞で読んだことを思いだすわ」とヘレンが言った。彼女は鼻先を指で触れた。そして眉を寄せた。「なんだっけな、忘れちゃった」と彼女は言った。
カールは靴をもう一度履いた。そして両足を明かりの下に伸ばして、靴を揃えて眺めてみた。
「何を読んだんだって?」とジャックが言った。
「何が?」とヘレンが言った。
「新聞で何か読んだって言っただろう?」とジャックが言った。
ヘレンは笑った。「私はちょうどアラスカのことを考えていたのよ。それで思い出したんだけど、氷詰めになった原始時代の人間が発見されたのよ。それを何かで思い出したの」
「それはアラスカの話じゃないよ」とジャックは言った。
「違うかもしれない。でもとにかく私は思い出したのよ」とヘレンは言った。
「なあ君たち、アラスカのことはどう思うんだよ?」とジャックは言った。
「アラスカになんか何もないさ」とカールは言った。
「彼、落ち込んでるのよ」とメアリが言った。
「君たちはアラスカでいったい何をやるんだ?」とジャックが言った。
「アラスカでやることなんか何ひとつないさ」とカールが言った。彼は両足をコーヒー・テーブルの下に入れた。それからまた外に出して、明かりの下に置いた。「誰か新品の靴は要らないか?」
「あの音はいったい何かしら?」とヘレンが言った。
彼らは耳を澄ませた。何かがドアをかりかりとひっかいていた。
「シンディーみたいだな」とジャックが言った。「中に入れてやったほうがいいだろうな」
「立ったついでにポプシクルを持ってきてくださる?」とヘレンが言った。彼女は頭を後ろにそらせてけらけらと笑った。
「私ももうひとつ欲しいわ、ハニー」とメアリが言った。「あら、まちがっちゃったかしらね。ジャックって言うつもりだったんだけど」とメアリは言った。「ごめんなさい。カールに話しかけてるような気がしちゃったから」
「みなさんにポプシクルね」とジャックが言った。「君はポプシクル欲しいかい、カール?」
「何だって?」
「君はオレンジのポプシクルを欲しいかい?」
「オレンジのを頼むよ」とカールは言った。
「ポプシクル四人前」とジャックは言った。
まもなく彼はポプシクルを持って戻ってきて、みんなに配った。彼は腰を下ろしたが、一同はまたひっかく音を耳にした。
「何か忘れてたような気がしたんだ」とジャックは言った。彼は立ち上がって玄関のドアを開けた。
「これはこれは」と彼は言った。「こいつはすごいや。シンディーはどうやら今晩はディナーを取りに行っていたようだよ。なあみんなこれを見てみなよ」
猫はねずみをくわえて居間に入ってきた。歩みを止めてみんなを見回し、それからそれをくわえたまま廊下の方に歩いていった。
「あれ見た?」とメアリが言った。「あれこそ落ち込みものよね」
ジャックは廊下の明かりをつけた。猫はねずみを廊下からバスルームへとくわえて移した。
「あの猫、ねずみを食べているんだ」とジャックは言った。
「私のバスルームでねずみなんか食べてほしくないわ」とヘレンが言った。「あの猫を追い出してよ。子供たちのものもいくつかあそこに入っているんだから」
「あいつはここからは出ていかないよ」とメアリが言った。
「ねずみはどうなるのかしら?」とメアリが言った。
「どうしたっていうんだよ」とジャックが言った。「もし俺たちがアラスカに行くとしたら、シンディーだって猟をすることを覚えなくちゃならないじゃないか」
「アラスカですって?」とヘレンが言った。「アラスカっていったい何のお話よ?」
「知るもんか」とジャックは言った。彼はバスルームのドアの脇に立って、猫のことをじっと見ていた。「メアリとカールはアラスカに行くって言ってる。シンディーは猟をすることを覚えなくてはならん」
メアリは両手で顎を支えるようにして廊下をじっと見ていた。
「ねずみを食べてる」とジャックは言った。
ヘレンはコーンチップの最後のひとつを食べてしまった。「彼に言ったのよ、バスルームで猫にねずみを食べさせないでくれって。ねえジャック」とヘレンが言った。
「何だよ?]
「猫をバスルームから追い出してって言ったでしょう」とヘレンは言った。
「そんなこと言ったってさ」とジャックが言った。
「何よこれ」とメアリが言った。「わああ」とメアリは言った。「この猫ここにきちゃったわよ」とメアリが言った。
「何してる?」とカールが言った。
猫はねずみをコーヒー・テーブルの下にひきずりこんだ。猫はテーブルの下に横になってねずみを嘗めた。猫は前脚でねずみをしっかり押さえ、ゆっくり嘗めた。頭から尻尾まで。
「猫は興奮しているんだ」とジャックは言った。
「ぞっとしちゃう」とメアリは言った。
「それが自然の本能なんだ」とジャックは言った。
「目を見てよ」とメアリが言った。「この猫が私たちを見る目を見てよ。うん、たしかにもう興奮しちゃっている」
ジャックはソファーのところに来て、メアリの隣に腰を下ろした。メアリはジャックの座る場所を作るためにカールの方ににじり寄った。彼女は片手をカールの膝の上に置いた。
彼らは猫がねずみを食べるのをじっと見ていた。
「あなた、猫に餌やったことないわけ?」とメアリがヘレンに訊いた。
ヘレンは笑った。
「みんなもう一服やらないか?」とジャックが言った。
「俺たちもう行かなくちゃ」とカールが言った。
「なんでそんなに急ぐんだよ」とジャックが言った。
「もっとゆっくりしていけばいいじゃない」とヘレンが言った。「別に何か用があるわけじゃないんでしょう」
カールはメアリの顔をじっと見た。彼女はジャックの顔をじっと見ていた。ジャックは自分の足もとの敷物の上の何かを見つめていた。
ヘレンは手のひらにのせたM&Mを結局全部食べてしまった。
「私、緑のやつがいちばん好きだわ」とヘレンが言った。
「朝には仕事に行かなくちゃならない」とカールはいった。
「この人ほんとに落ち込んじゃってるんだから」とメアリが言った、「シラケ鳥ってのを見てみたいと思う? これがまさにそれよ」
「君は一緒に来る?」とカールが言った。
「ミルクを飲みたい人はいるかな?」とジャックが言った。「ミルクなら少しあるんだけど」
「クリームソーダでがぶがぶになっちゃったわ」とメアリが言った。
「クリームソーダはもうない」とジャックが言った。
ヘレンがけらけらと笑った。彼女は目を閉じて、それからまた目を開け、もう一度けらけらと笑った。
「我々は家に帰らなくちゃならないんだ」とカールは言った。そしてほどなく立ち上がってこう言った、「コートは着てきたっけな、いや、着てなかったよな」
「なんですって? コートは着てなかったと思うけど」とメアリは言った。彼女はまだ腰を下ろしたままだった。
「もう引き上げよう」とカールは言った。
「この人たちもう帰るって」とヘレンが言った。
カールはメアリの脇の下に両手を入れて、抱え上げた。
「みなさん、それでは」とメアリが言った。彼女はカールを抱きしめた。「私、おなかいっぱいで動けない」とメアリが言った。
ヘレンが笑った。
「ヘレンにかかったら何でもかんでもおかしいんだから」とジャックが言った。そして彼は笑顔でヘレンに訊いた。「なあ、何がおかしいんだい?」
「わかんないわ。何かメアリの言ったことがおかしかったのよ」とヘレンが言った。
「私、何を言ったのかしら」とメアリが言った。
「思い出せない」とヘレンが言った。
「もう行くよ」とカールが言った。
「じゃあな」とジャックが言った。「御機嫌よう」
メアリが笑おうとした。
「さあ行こう」とカールが言った。
「おやすみ」とジャックが言った。「おやすみ、カール」カールはジャックがすごくすごくゆっくりとそう言うのが聞こえた。
外に出ると、メアリはカールの腕をつかんで、下を向くようにして歩いた。二人はゆっくりと歩道を歩いた。彼は彼女の靴がたてるひきずるような音を聞いた。少し離れたところで犬の吠える鋭い声が聞こえた。そしてずっと遠くの車の音が、それにかぶさるように聞こえた。
彼女は顔を上げた。「ねえカール、家に帰ったら私ファックされたい。何か話してもらいたいし、気を晴らしてほしい。私の気を晴らしてよ、カール。今夜は気晴らしをしたいのよ」彼女は彼の腕をつかんだ手をぎゅっと握りしめた。
彼は靴の濡れた感触を感じることができた。彼はドアの鍵を開け、明かりをつけた。
「いま行くよ」と彼は言った。
彼はキッチンに行って、水をグラスに二杯飲んだ。そして居間の明かりを消し、壁を手探りしながらベッドルームに行った。
「カール!」と彼女は叫んでいた。「カール!」
「大丈夫、俺はここにいるよ!」と彼は言った。「明かりのスイッチを探しているところだよ」
彼はスタンドを見つけた。彼女はベッドの上に体を起こした。彼女の目はきらきらとしていた。彼は目覚まし時計のノブをひっぱり、服を脱ぎはじめた。彼の膝はがくがくと震えていた。
「何か吸えるものない?」と彼女は言った。
「俺たちのところはそういうもの置いてない」と彼は言った。
「じゃあお酒を作ってよ。何か飲みたい。お酒もないなんで言わないでよね」と彼女は言った。
「ビールがちょっとあるだけだよ」
二人はじっと顔を合わせた。
「ビールを飲むわ」と彼女は言った。
「本当にビールが飲みたいのかい?」とカールは言った。
彼女は肯いて、唇を噛んだ。
彼はビールを持ってきた。彼女は彼の枕を膝の上に載せて座っていた。彼は彼女にビールの缶を渡すと、ベッドの中にもぐりこみ、布団を引っぱりあげた。
「ピルを飲むのをわすれてた」と彼女は言った。
「なんだって?」
「ピルを忘れた」
彼はベッドを出て、彼女のピルを取ってきた。彼女は目を開けた。彼は錠剤を出して、彼女が伸ばした舌の上に置いてやった。彼女は錠剤をビールで流し込み、彼はベッドにもどった。
「これ持ってよ。私もう目を開けていられない」と彼女は言った。
彼は缶を床の上に置き、横向きになって暗い廊下をじっと見つめた。彼女は腕を彼の脇腹の上に載せ、胸に指を這わせた。
「アラスカに何があるの?」と彼女が言った。
彼はうつぶせになり、ゆっくりと自分の側に移動した。ほどなく彼女はすうすうといびきをかき始めた。
明かりを消そうと身を起こした時に、彼は廊下に何かが見えたような気がした。じっと見つめていると、もう一度それが見えたように思えた。一対の小さな目だ。胸がどきどきした。彼は目をこらしてじっと見つめていた。手を伸ばして、何か投げつけるものがないかと探した。彼は靴の片方を手に取った。そしてまっすぐに身を起こし、両手に靴を握りしめた。彼女のいびきが聞こえた。彼は歯を食いしばった。彼はじっと待った。彼はそれがもう一度動くのを、どんな小さな音でもいいからたてるのを待った。
好き…
夜、メンマ、抹茶、麻婆豆腐、揚げたてコロッケ、鯵の干物、古典落語、猫
嫌い…
朝、レバ刺し、らっきょう、玉子かけご飯、満員電車、安倍晋三