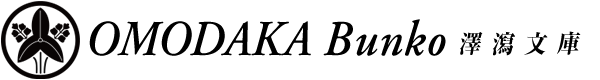映画がとても良かったので、こちらも読んでみました。
こんな本が出ているとは知らず、図書館で見つけたときにはちょっとしたサプライズで、無条件で貸出カウンターに持っていきました。
著者は本映画のイタリア人監督で、ジョゼッペ・トルナトーレという人。本書の原文も当然イタリア語。
僕的にはなじみの無かった人なのだけど、訳者の「あとがき」に書かれているとおり、『ニュー・シネマ・パラダイス』の監督と知って、はは〜んと納得。
原案から脚本、そして監督を一人でこなして、小説仕立ての本もだす。
羨ましい才能です。
どれかひとつだけの才でも、人は羨むのに…
その「あとがき」にもあるとおり、本書は『一般的な意味での〈映画の原作小説〉ではない。直接映画に用いられたシナリオでもなく、事後に再構成されたノベライズでもない。』とのことである。
著者本人も小説の体裁を成してはいないと、あくまでシノプシスの次順に書かれた草稿であると言う。映画の撮影に入る前に様々な関係者、プロデューサー、配給会社を説得するため、脚本執筆の前段階の少し長めに書かれた草稿であるという。
そして結果的には、その簡潔さがとてもいいのです。
もう少し詳細に、もう少し詳しく、もっと長くと思う気持ちも無いわけではないけど、この簡潔さが一定の緊張感とテンポを生み出しています。
でも物語は濃密です。
雄弁でも、多弁でもないけど物語は濃密です。
訳文の独特な句読点の打ち方、体言止めの多用などに、はじめはかなり戸惑ったけど、結果としてそれも潔い簡潔な文体を際立たせている。
僕ははじめに映画の方を観て、そしてこの本という順番だったので当然読み進みながらも次の展開、その次の展開、そして結末まで知っていたわけだけど、読み進みながら映画での各シーンを思い出し、はは〜んとうなずいたり、そうだったのかと納得したりとドキドキ感には事欠きません。
言い古された表現だけど、簡潔で潔い文体のおかげでかえって「行間」の奥行きが深くなってきます。奥行きの色数も増えています。
不要な形容詞や慣用句はかえって読み手の想像力の広がりを阻害し、貧困にさせてしまうということに改めて認識を深くしました。
感情表現はほとんどなく、動作、行動の表現が多いのも映画的、シナリオ的な手法なのでしょう。次々に物語は展開し、場面が切り替わり、登場人物が交錯し、そして大団円を向かえようとした時に、読み手は裏切られることになります。
サスペンス物やミステリーとは全く違うタイプのどんでん返しとなります。
そしてここに至って、俄然、主人公のヴァージル・オールドマン氏に感情移入してしまうのです。
最終行で『そして彼は待ちはじめた。』とあるとおり、本書は序章なのです。
もちろん、続編が出版されたり、『続・鑑定士と顔のない依頼人』が映画化されることもない。
ある種の映画や小説に稀にあることだけど、主人公の「その後」が気になってしょうがないことがあります。映画のエンドロールが出て、あるいは本を閉じて、ホッとしたり、納得したり、笑ったり、泣いたり、誰かとハイタッチしたりすることなく、その後が、主人公のその後が気になって、気になってしょうがない物語。
『鑑定士と顔のない依頼人』とは、そんな小説で、そんな映画です。
僕もDVDのジャケット写真を見るたびに、『ああ。ヴァージル・オールドマン氏はその後どうしているのだろう…』と気になってしょうがないのです。パイレーツ・オブ・カリビアンを観ていても、ジャック・スパロウのことなどどうでも良くなって、ヴァージル・オールドマン氏はその後も、レストラン『ナイト・アンド・デイ』の一席に座り続けているのだろうかと想いを巡らし、同時に胸がギュッと締めつけられるのです。
よくあることだけど、小説を読んで面白かったのに、映画化に期待して観て、ガッカリするということがあります。まあ、現実にはこの方が多いのでしょう。
『鑑定士と顔のない依頼人』は映画も良質で、そして本も良質という数少ない例になるのだと思います。
好き…
夜、メンマ、抹茶、麻婆豆腐、揚げたてコロッケ、鯵の干物、古典落語、猫
嫌い…
朝、レバ刺し、らっきょう、玉子かけご飯、満員電車、安倍晋三